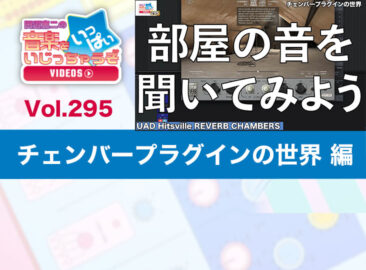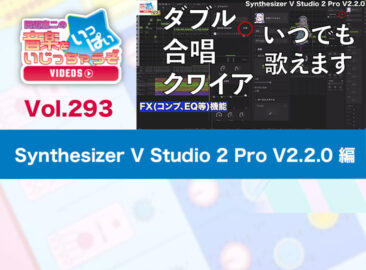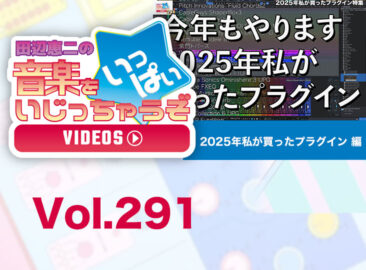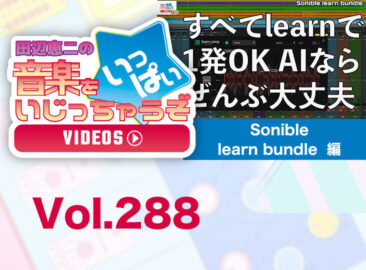第一線で活躍するクリエーターのインタビューやコラムなど、音楽と真摯に向き合う作り手の姿があなたの創作意欲を刺激します!
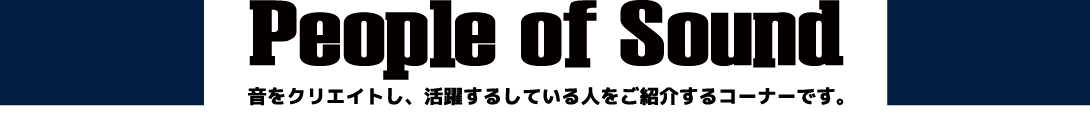


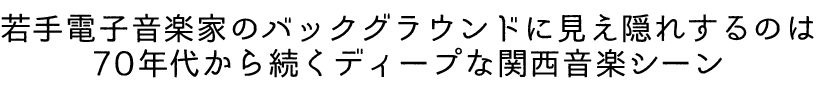
第35回目は、アーティスト Seihoさんです。テン年代の日本電子音楽シーンを代表するSeiho。若手音楽家の異才は、大阪を活動拠点にしながら、ニューアルバム「Collapse」でワールドワイド・デビュー。そんな彼を、ホームである大阪でつかまえインタビュー実施。エレクトロミュージックの先端を走る彼ですが、バックグラウンドに見え隠れするのは70年代からディープに続く関西音楽シーン。興味深いインタビューになっています!
2016年5月2日取材
取材協力: epok/CHIKA-IKKAI (http://epok.jp/)
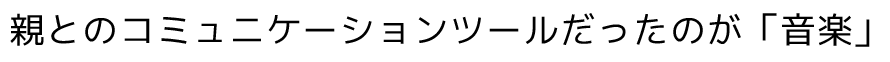



音楽に触れられた頃のお話をお伺いできますか?
父親がジャズ、特にビバップが好きだったんですが、その影響で幼稚園の頃から自然と黒人音楽を耳にしていました。実家は寿司屋なんですが、お店のバイトにヒップホップのDJをやってる人もいました。90年代前半にACID JAZZの流れがありましたが、関西のFM802などでもよく流れていたので、そういうのを耳にしていました。一方母親も音楽好きで、僕が産まれるまでディスコに通ってたそうです。現在、ニューヨークでジャズサックスプレーヤーをやってる弟がいるんですが、小さい頃は父親と兄弟の3人で月1回程度タワーレコードに行き、好きなCDを1枚買ってもらう、みたいな感じでした。音楽は親とコミュニケーションを取るためのツールという感じだったんです。

音楽的に恵まれた素晴らしい環境ですね!
その後、小学生になるとフュージョンも好きになって、特にSTUFFが大好きだったんですが、コーネル・デュプリーが好きでギターが欲しくなり買ってもらいました。小学4年〜6年の間、街のクラシックギター教室みたいなところに通って習っていました。

そんなに早熟だったら、同級生から浮いてませんでしたか?
いや、音楽はあくまで親とのコミュニケーションツールだったので、音楽を友達と共有するようなことはしてなかったんですよ。友達と音楽について話すようになったのは、中学以降ですね。クラスの中でも、自分で言うのも何ですが、割と笑いの中心にいる存在だったので、「音楽が僕を救ってくれた。。」みたいなエピソードは当然なく、孤立して独り音楽を聞いてる、ということではなかったです(笑)。

なるほど。では、バンド活動はされましたか?
ギターが弾けたので、中学生になったら先輩にバンドに誘われて、そこで初めてロックを聞くようになりました。Green Dayとか、BlinkとかNOFXを聞かされたんですが、「アドリブどころかソロも無い!すごい音楽やなぁ。」と思いました(笑)。加えて、The JB’sを始めとするファンクも好きだったので、トロンボーンやりたいと思ってブラスバンド部にも入りました。高校は、やっぱりジャズをやりたいと思っていたので、ビッグバンドがある学校を選びました。

う〜ん、渋いですね!ビッグバンドがある高校は少なかったんでは?
そうなんです。当時、大阪にはビッグバンドがあるのは2校しかなかったんですが、今だと、映画「スイングガール」の影響で結構増えてるみたいです。高校に入ったら、僕と同じようにビッグバンドに入る事を目的に入学して来た人が結構いたんで、トリオを組んで演奏したり、ジャズ喫茶に一緒に通ったりしてました。
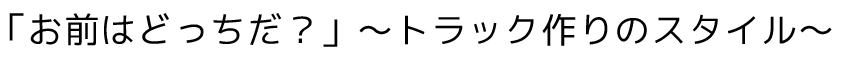

ギターやトロンボーンといった楽器が弾けた訳ですが、自分で音楽を作りだすのはいつからですか?
小学5、6年の頃、パソコンを買ってもらったんですが、当時、「ウゴウゴルーガ」や「ポンキッキーズ」の影響もあり、CGクリエーターになりたかったんですが、CGをやるにはパソコンのスペックも高くなければいけないし、必要な知識も追いついてなかったので難しかったんです。中学2年になって、ローランドのミュージ郎、音源のSC8850とMIDIキーボードを買ってもらい、音楽を作り始めました。
実家の寿司屋でバイトをしていたヒップホップのお兄さんがアドバイスしてくれて、当時、「AKAIのサンプラーを買ってネタ中心にトラックを作るパターン」か「R&B系の楽曲を一から打ち込むパターン」に大別出来るが「お 前はどっちだ?」みたいなことを言われたんです ( 笑 )。 僕はサンプリングが何なのかよく理解してなかったので、シーケンサーの方を選びました。そうやって音楽を作り始めるんですが、その時期、半野喜弘さん、レイハラカミさん、青木孝允さんみたいな方々が登場し、クラブに足を運ぶようになる一方、バンドではオシリペンペンズなどの「関西ゼロ世代」が出て来て、関西はとても面白かったんです。中学〜高校の間は、もともと好きなジャズに加え、関西で展開されるそういったシーンにも影響を受けていました。

ジャズ・トロンボーンプレーヤーと、電子音楽制作を同時期にやってたんですね。
はい。トロンボーンに関してはコンクールでソリスト賞をもらったこともあり、音大に進学しようとも思っていました。でも、高校3年の時に外国人のすごい演奏を目にし、「これは勝たれへん。。」とプレーヤーとして挫折してしまいます。そこで、逃げ道と言ったらおかしいですが、僕には電子音楽があったから、真剣に極めたいと思ったんです。丁度その頃、Ametsubや、青木孝允さん、ツジコノリコさんといったアーティストの動きが活発になっていて、イベントに足を運んだりリリース作品を追いかけるようになりました。ジャズより電子音楽をやってみたいと思うようになり、普通大学に進学し楽曲制作を続けました。
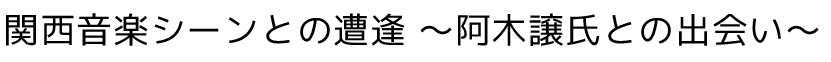

大学生の頃、ご自分の周りには電子音楽〜エレクトロニカのシーンはありました?
京都の大学でしたが結構ありました。ライブハウスの京都MOJOとか、クラブのWORLD TOKYOもありましたし。その時期に、ポップユニットSugar’s Campaignの相方になるAvec Avecとも出会いましたし、シューゲーザーやポストロックのシーンにいるバンドの人達とも繋がりました。その中で曲が作れるとなると人数がかなり限定されてくれるので、そこで知り合ったクリエーターと集まるようになりました。

関西で活動してると、東京の情報がメディアを通じて入ってくるじゃないですか。そういった情報に対しては、どんな感じで受け止めてました?
正直、東京はあまり見てなかったんですよ。どちらかというと海外、特にアメリカのシーンの動きが面白くなってたんです。Flying Lotusのようにヒップホップやってた人達が、ラッパーなしのインストを作ったり。MySpaceをステージにして、そういったビートメーカー達が上に登り詰めて行く、みたいなそういう動きが面白かったんです。

キーワードとしてネットが入ってくるわけですね。一方、関西には昔からインディペンデントのシーンが大きくありレーベルも沢山あった訳ですが、ご自分のレーベルをスタートされますよね?そのあたりをお伺いできますか。
大学卒業する少し前に、音楽評論家の阿木譲さんと出会いました。阿木さんはnu thingsというクラブをアメリカ村でやってらっしゃるんですが、そこに行き場の無いエレクトロニック・ミュージシャンが集まってたんですよ(笑)。

阿木譲さん!重鎮ですね!どういうことですか?(笑)
ヒップホップだけどラッパーなしのインストを作るビートメーカーや、電子音楽を使ったバンドなんだけどちょっとCHILLが入った感じとか、そんな音楽をやってる人達が「俺らどこ行ったらええんやろ〜」という感じで集まって来たんです。2008〜2009年頃ですね。同時に海外ではChill Waveみたいな動きもあって、僕らの動きと似たような感じもあったんです。
阿木さんがやってらっしゃった雑誌「ロックマガジン」やレーベル「ヴァニティ・レコード」の話や、所属してたPhewやEP-4といったアーティストの話を色々聞かせてくれ、「自分たちでも出来るんじゃないかな」と思ったんです。DIYと言っちゃうとちょっと意味合いが違いますが、自分たちの力で自分たちの音楽をかっこ良くやる精神というか、、、そこでレーベル「Day Tripper Records」を2011年に立ち上げたんです。

世代を大きく隔てても、音楽を軸にインディペンデント精神が繋がっていますね。それは関西シーンだから実現したのかもしれません。
はい、同世代はもちろんのこと、上の世代とも繋がれるところが僕が音楽をやっていて好きなところなんです。阿木さんとお話するのが好きなんですが、同じ志しを持った先輩方と音楽を通じて繋がるのは素晴らしいです。
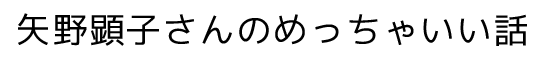
めっちゃ優しい方なんですが、面白い話があるんですよ!レーベルを始めるにあたって、2015年までの目標を立てたんです。レーベルをどこまで持って行きたいとか、こういうことをしたいとか。それが良くも悪くも2013年に叶ってしまったんです。それで2013年頃から少し目標を見失った感じが続いてしまって、2014年〜2015年は自分の中で何も無い時間というか先に進まない時間だったんです。もしかするとそれは僕だけの話ではなく、シーン全体にも通じる話かもしれません。海外の動きを見てても、その頃は面白かった新譜をリストアップすることができない、みたいな感じだったんです。
そんな時期に丁度、矢野顕子さんと曲作りをする機会を頂き、そういった自分の悩みを相談してみたんです。「自分たちの音楽シーンが一周してしまって冬の時期に入ってしまい、次の周回に向けて動き出すということが少し怖いんです。」みたいな感じで。すると矢野さんは、「回ってるのは自分じゃなくて、外を照らす灯台の光が回ってるんであって、その光がたまたま遠くに行ってしまっただけ。だから今は暗く感じてるけど、また時間が経てば自分達を照らす時がやってくるのよ」と言って頂きました。「光が自分から離れた場所を照らしてるからといって、そっちに動いちゃうと、光の早さには勝てない訳だから一生光に会う事ができないでしょ。落ち着いて待ってればいいのよ」と。

さすが、重みがある言葉ですね!
そうなんですよ。「めっちゃいい話やな〜」と思って色んなインタビューでこの話をしてたんです。で、この前、矢野さんにお会いして、「あの時の話、色んな所で言ってるんですよ〜。」と伝えたら「私、そんなこと覚えてないけど、私は灯台だから大丈夫!」と言われたんです(笑)。「すごい人だなぁ〜」と思いました。「ぜんぜん次元が違うなぁ〜」と(笑)。

では、機材のお話をお伺いしたいんですが、ミュー次郎/Sound Canvas以降のシーケンサーは何を使われましたか?
ループを作る機能がすごいという評判があったのでACIDを選びました。その後、大学生になり、周りのクリエーターからの評価も大きかったのでAbleton Liveに乗り換えました。パソコンはずっとWindowsを使っていて、MacBookに変えたのはここ2年くらいなんですよ。

今日はこうして沢山のシンセをセットアップして頂いていますが、初めて買ったシンセは何ですか?
microKORGです。それまでは、先ほど言った通りRoland SC8850を始めとするラック音源を結構使ってました。制作においてアナログとデジタルのどっちがいいか、みたいな考え方はしないんです。そんな事よりも、いかに自分の手を動かして自分の音を作っているかということを大事にしています。

API500互換のアウトボードも結構ありますね!どんな使い方をされていますか?
最初、自分に必要ないかなと思っていたんですが、まとまったお金が入ったタイミングで試しに買ってみたんですよ。そしたら嬉しいことがあったんです。アナログなので、音を作りDAWにオーディととして流し込むには毎回、その曲の長さの時間をかけてプレイバックする必要があるじゃないですか。「その時間がなんかいいなぁ。」と思えたんです。
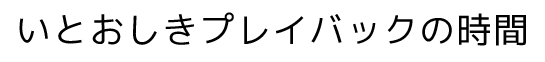

ソフトシンセだったらオーディオ化するために、曲の頭からお尻までプレイバックする必要はありませんもんね。
ユーザーからのビンテージ Prophet に近づけて欲しいという リクエストに応えた Dave Smith Instruments Prophet ’ 08 PE。 現代アナログシンセの best of the old school。
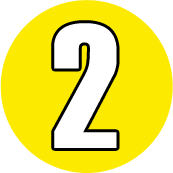
セレクトされた機材はアナログ / デジタル、旧 / 新の区別なくフラッ トな視線でチョイスされているの が特徴だ。

新作アルバムでは、サウンドの軸 となったというアナログモジュ ラーを多数ラックマウント。その 並び順にも意味があるという。。

Moog Mother-32:Moog 社初め てのテーブルトップ型セミ・モ ジュラータイプのシンセ。Moog ラダーフィルターがサウンドに アクセントをもたらす。
今はこの時間が嬉しいと思えるんですよ。パソコンだけで、例えば3分の曲を作る場合、サウンドや構成の最終イメージが頭の中で割と明確に浮かぶので、今だったら2分とかで作れちゃうんです。もちろんその場合は聞き返すこともしないです。でもアナログデバイスを使うようになり、コーヒーを淹れたりして落ち着きながら改めて聞き返す時間を手にすることになった訳ですが、そんな時間の経過を、改めていとおしく思えるようになりました。音楽制作時の時間のかけ方は、アナログ環境の方が好きですね。

途中で立ち止まって、ゆっくりと考えてみる時間が確保できたということもあるんでしょうね。Seihoさんはギターもやってらっしゃったので、コード等の知識もある訳じゃないですか。曲の作り方ですが、アナログシンセを使ってサウンドを作る場合、どんな感じで行うんですか?
楽曲に同期した感じで使う意識は無いんです。1〜2時間Recを回しながらアナログシンセを触り、素材としてどんんどん録るんです。僕は機材を触っている間に曲のアイデアが浮かぶといったタイプではなく、最初から頭の中に曲の全体像がパンと浮かぶタイプです。だから、アナログシンセを使って録り貯めた素材は、すでに構想された楽曲に対してランダムな要素を加えていく要素、といったイメージなんです。
モジュラーラックを自分の右手に置くか、または左手に置くかでも出てくる音が違うし、また、ラック内のモジュールの並べ順によっても出てくる音が違うので、こういった予測不可能な要因を自分の楽曲の中に取り込んでいくイメージです。逆に、いろんな試行錯誤を繰り返した後に、本当に自分が作りたかった音が見えてくるというケースもあったりします。面白いですね。確かにソフトシンセは便利ですが、こういった部分はハードに取って変われない部分だと思います。
あと、ずっとピカピカ光り続けてるというのもヤバイですね(笑)。僕がトイレに行ってる間も、「こいつらずっと光りながら音を出し続けてるんや〜」とか。それはすごいなぁと思います(笑)。
記事内に掲載されている価格は 2016年7月13日 時点での価格となります。
最新記事ピックアップ