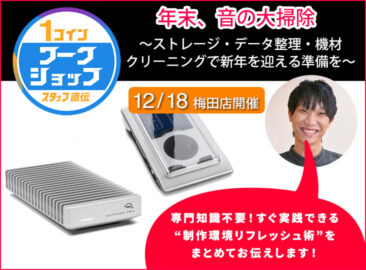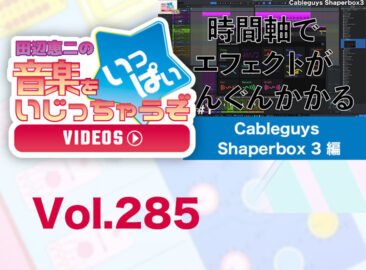あなたの楽曲制作にヒントをもたらす数々のノウハウ記事に加え、膨大な動画コンテンツは制作トレンド&Tipsの集大成!

シリーズ第2弾として 「徹底討論!アウトボードは要るのか?要らないのか?」 というテーマで、ワタクシ澤田と渋谷店スタッフ安田、そしてアウトボードといえばこの人的な豪華ゲストを交えて徹底討論させて頂きます。ワタクシ澤田はわかりやすく「アウトボードはあった方が良い派」でして、一年中この手の相談を受けている身でもあります。
それに対して、渋谷店スタッフであるPD安田は「アウトボードってなくてもよくない派」だったりもします。もちろん使ったことが無い訳ではなく、色々な機材が進化を経て今となっては、もはや必須アイテムではないのでは?といった意見をもってます。今回、彼から改めて「なぜ要るのか?」をじっくり聞いてみたいという申し出がありまして、せっかくなのでこのやりとりを記事化することで、同じような疑問を持っている方にも参考になるのではないかと考えております。
スタッフ二人が趣味嗜好で話すだけでは説得力が少々弱いなと思いまして、様々な媒体でお見かけしたことがあるだろうアナログ機器の壁のスタジオオーナーのといえばこの方!株式会社Cubic Records代表「鈴木Daichi秀行」さんをお迎えして、色々実験しながらお話をさせて頂こうと思います。
●ゲストプロフィール
Sound Produce、作曲、編曲、Guitar、Bass、レコーディング&ミックスエンジニア
バンドからシンガーソングライター、アイドルまで幅広いサウンドメイクに定評がある。
近年は自主レーベル「Cubic Records」を立ち上げ、数々の作品をリリースしている。
最初に手が伸びるマイクプリは?
Rock oN 澤田(以下、S):よろしくお願いします!本日はご協力いただきまして誠にありがとうございます!
まずは簡単なお話からさせて頂ければなと思います。最近、Daichiさんがボーカルを録るとなったときに最初に手が伸びるマイクプリってなんですか?
鈴木Daichi秀行 氏(以下、D):最近はRupert Neve Design Shelfolf 5025ですね。なんかちょうどバランスが良いというか。
S:意外といい意味でスタンダードですね。確かにこの機種は周波数的に飛び出てるとこも、ひっこんでるところもない感じですよね。全帯域に厚みがあってしなやかというか、老若男女問わず使える印象があります。
D:まあ、 ヴィンテージのNeveももちろん素晴らしいけど、ポップス系のファーストチョイスだとこれかな。ここに来るエンジニアもこれを使う人が多いです。曲によっちゃうと思うけど。守備範囲が広くて使いやすいと思います。

※手の届きやすいラックの一番下にマウントされてました
S:ありがとうございます。どんどん行きます!お次にギターを録る時のファーストチョイスになるマイクプリは何ですか?
D:ギターはこれ。Chandler Limmited のTG-2のBack to Basicモデルです。

※上から3個目の赤いノブ
S:お、しかもBack to Basic(日本限定カスタムモデル)なんですね。
D:元々、ノーマルの時点で結構カラッとしてていいんだけど、ちょっとだけ低音が薄くなっちゃうから、それをうまいことチューニングしてあるタイプだね。
S:僕もギターにTG-2は大好きです!明るくちょっとジャリっと感あって、中域も程よく濃いのでギターは本当にあいますよね。ちなみに個人的にはあのRoger Mayerの456HDと456の上にあるEQ(Dottore XFM)のセットを持ってる時点でやばいです(笑)

D:ふふっ(笑)上のEQは電源いらないんだよ。珍しいパッシブのEQで低音がすごくいい感じになる。
S:456HDに辿り着いたクリエイターさんはDottore XFMも導入されますよね。このハードってTape系プラグインほどわかりやすくかからないから、ほんとのテープ経験者世代にしかわかんない当たりかたするんですよね。テープなので低音が膨らみます的な感じじゃなくて、テープに録ったときのコンプレッション感とかムチっと感がうっすらつく感じ。ただそれができる機材も少なくて、かなり玄人アイテムですね。流石です!
ハードウェアは、あった方がいい?無くてもいい?
S:アウトボードの博物館みたいなスタジオなので、いくらでも続けられますが、本題に入らせて頂きます。
今回は「ハードウェア(特にマイクプリ)は、あった方がいい?or 無くてもいい?」のテーマに議論をしていかせて頂きます。
Rock oN PD安田(以下、Y):僕が先にお伝えした通り「ハードウェア無くてもいいんじゃないか派」です。
S:で、僕が分かりやすい「ハードウェアあった方がいいんじゃない派」です。
まず「無くてもいいんじゃないか派」の安田くんのお話を聞いてみて、次に「あった方がよくない派」の僕の話を聞いてもらい、双方の話を聞いてどう思うかをDaichiさんにもお話してもらって、各々が最終的にどう思うか?ってのが今回の流れになります。
D:僕もこの手の話ってすごく聞かれるんだよね。で、うちのスタジオで違いを体験した人は大体なんか1個(アウトボードを)入れてみようってなることがほとんどかな。作業をする際に実際に通す通さないをするから結果の違いをその場で体感できるからね。
S:ほとんど本テーマの答えですね(笑)実際に違いを体験すると自分でもやってみようかなってなるのがアナログの魅力ですよね。

Y:さてまず私「無くてもいいのでは?派」になりますが、前提として話しますと、僕はマイクプリ然りアウトボードに対して完全な否定派ではなくて、基本アウトボードは大好きです。過去に自分でもまあまあ買ってまして、それこそdaichiさんのスタジオの記事とかよくお見かけしてて。「これだけ揃えなきゃダメなのかな」って、当時は思いつつも。当然たくさんは買えないので、部分的に買ったりとかして試してました。ただ最近になってきてから、お客さんと電話とかで話してる時に、果たして本当にいるのかなって思うことが増えてきてまして。で、ちょっとそこにメスを入れるわけじゃないですけど「本当のところどうなんですか?」みたいなのを聞いてみたいと思っていました。僕は「綺麗に録る」を前提にすると、使わない方がいいかもと思ってます。

S:まあ、ある一定以上のインターフェースならっていう前提があるのは共通の認識として、安田くんの言う「綺麗」ってどういう感じですか?
Y:雑味がないというか、何かを間に繋ぐことは少なからず鮮度が落ちていく印象があります。そういう意味では直接の方が綺麗に録れるかなと思ってます。また昔は今ほど情報があんまりなかったんで、ハードウェアを入れなければ音は良くならないし、持ってなきゃダメでしょうってのが多数派だったんですが、適切なレベルに持っていくという意味では「直」でいいんじゃない?って。
S:その「直」って部分をもう少し詳しくきける?
Y:直とは、マイクプリを使わずに「インターフェースに直接録る」ということなのですが、最近の機種って、2〜3万のインターフェースでもまあ綺麗に録るっていう意味では録れますよね。なので、昔の製品の印象に比べるとそのまま直で録っても綺麗だなと思うんです。
S:それは俺も思います。聴いたり弾いたりする分には何も問題ないよね。特にRME、Apogee、Universal Audioとかいけば余裕だし、SSLとかAudientの手頃なのでも全然ちゃんとしてる。
Y:そうなんですよ。それこそ10何年前とかのいわゆる入門のインターフェースに直だと、音がこもるというかちょっと中域に集まるというかなんか残念な感じでしたけど、今は直でレコーディングしてて音が悪いと思うことがなくなりましたよね。確かに上位機種に比べてS/Nがよくないとかはもちろんあるんですが、いい意味で普通ですよね。
S:うんうん。それを踏まえた上で僕なりの解答は、Universal AudioのApolloシリーズみたいな特殊な例を抜かすと、インターフェースの音のキャラクターって基本1〜2個しかバリエーションないじゃない?ギタリストとかだと実感したことあると思うんですが、アンプ直の音はかっこいいし、抜けや反応がいいよね。でも全部の場面でそれだけでは対応出来ないじゃん?ってのがありまして。で、クリーンやクランチにしてから、歪みのエフェクターとかブースターをかますことでより狙った音にしたりとか、各場面にあった色をつける必要があって。後、やっぱ人間は感覚センサーが優秀なのか、リアルタイムに聴いてる音で演奏が変わるよね。歌でもなんでも。やっぱりレコーディングの段階でゴールみたいな色がついている方がテイクが良いって実感があるから。

D:実際に普段宅録をしているアーティストがうちのスタジオに来て歌いやすさとか演奏しやすさに驚いてる姿はよく見る。パフォーマンスに直結するよね。ただ、だからって高いのを絶対買わなきゃいけない訳では無いよね。そのソースに合う事が重要で値段じゃない。
S:そこは絶対そうですね!マイクもマイクプリも値段より相性が絶対だと思います。
まとまった資金でステップアップする際の優先順位には!?
S:と、双方の見解はこんな感じでした。少し質問を変えてみます。僕らが店頭でよく聞かれる話のひとつでもあるのですが、ある程度のまとまった資金でステップアップを考えている的な相談です。例えば予算50万くらいでなんかを買おうと思いますって時に「マイク」「マイクプリ」「インターフェース」という選択肢があった場合、優先順位的にどうだと思いますか?
D:絶対マイクだね。マイクが一番音が変わるもんね。音が出る場所に近い方からちゃんと揃えていくのがいいと思う。いいマイク、それに合わせて補完するマイクプリの順かな。
S:ありがとうございます。皆さん、まずはマイクです!竿モノの人はマイクに当たるマイクプリDIにこだわりましょう!先ほど聞き忘れましたが最近よく使うマイクはありますか?
D:最近はELA M251をよく使うかな。あと、SoyuzのFETの方。

S:ここ数年のElamの人気はすごいですよね。元々年に1〜2回くらいしか入荷しないので今からだと2〜3年待ちな感じです。今ではかなりの機材があるわけですが、Daichiさんが最初に買ったマイクってなんですか?
D:RODE NT2だね 現行の NT2Aの前のモデル。それこそ20年くらい前かな。手の届きやすい値段のコンデンサーマイクが初めて出てきた感じだった。
S:それでも6〜7万はしましたよね。それ以外がAKGのC414かNeumannのU87 Aiかみたい時代ですもんね。みんな持ってるレベルでしたもんね。
D:うん。ボーカルやアコギの録音とかに使ってそのまま製品になってる曲とかもある。初めてのコンデンサーマイクでキラキラした音が出てビックリした思い出。
Y:その当時って何に録るんですか?MTRとかですか?
D:ADATとYAMAHAの02Rのセットだったね。プラグインとか純粋にだって、WavesのNativePowerPackとかしかなかったしね。Renaissanceシリーズすらまだ無かった。DUYとかもあったけど高かったし。
S:そうなの。DAWもマシンパワーが足りなくて今みたいに使えないし、プラグインとかもほとんどなかったのよ。僕も01Vを売ったお金でWavesのプラグインを買った記憶があります。ちなみに最初に腹括ったぞ!って機材って何ですか?
D:マイクプリはこれかな?Vintech X73。これも多分20年くらい前かな。当時はまだね、オールドの価値がまだ今ほど高くなくて、中身が本物Neveだった頃のBrent Averillでも 50万くらいで買えてたりしたもんね。だったら新しい方がいいんじゃない?みたいな。

Y:Vintechを最初に買った理由って何ですか ?
D:普通にもうNEVE系の選択肢があんまなかったんだよね。EQも含めて一番1073っぽくやってるのが、もうこれしかなかったと思う。
S:ですよね。僕は今でも大好きです。 NEVE系ってVintechかBrent Averillくらいしかなかったですもんね。で、EQ付となるとほぼ一択。Neveの新品の音がします!ヴィンテージみたいになまってないです的な謳い文句だったのを覚えてます。
ちなみにさきほどの僕と安田の話を聞いてみて、daichiさんなりのマイクプリの有無についてご意見を伺えればと思うのですが。
D:まずプリアンプをどう使うか?だと思うんですよ。そしてマイクプリはコンプのような側面もあると思います。インターフェースに直接でも記録するって意味なら録れるし、そうそう変な音にならないけど、プリアンプの様にインプットGAINがあって、アウトプットの調整が用意されない分、その先の作り込みの作業は出来ないというか、そもそもインプットを上げて、キャラクターを確立させるという使い方は多分想定して作られてないかなと。エンジニアとかがやってる作業って、キャラクターも含めてそのプリアンプのスイートスポットを見極めながら狙った音で録ってるわけで、そういう意味でアウトボードじゃないと出来ない部分があるかなって感じですかね。
Y:なるほどですね。ハードのマイクプリみたいにインプットとアウトプットの組み合わせが重要なんですね。インプットで音を作って、アウトプットレベルを適正にするみたいな。

D:うん。後、昔から残ってるメーカーってみんな機体のキャラクターがわかりやすいよね。例えば1176とかもそうだし、結局はあの音を通せばこの音になるっていうイメージがはっきりしてる。レコーディングの現場って時間がないから。その場でこのトラックはTubetechかな?こっちのトラックは1176かなみたいな?。って感じでサウンドがイメージできるのが重要で、結局使い続けられてる機材はキャラクターで選ばれているという理由が大きいかと思います。
S:ですよね。色々覚えてくると、こういう結果にしたいからこのメーカーのこの製品ってなってきますよね。何か別の製品で録音してEQだCOMPだでいろいろするよりも、最初から狙った音になる機材を使うのが早いですもんね。
D:うん。で、やっぱり 1番はやっぱりインプットのGAINとアウトプットの出力調整が肝で。インプット上げて、もう飽和するぎりぎりまでとか、逆にいうと、オーバー目でやっても破綻しないってのもハードウェアのポイントかな。もっとシンプルな言い方すると「かっこいいからOK」みたいな。
Y:かっこいい音になるっていう判断が出来るようになるには、体験しないてみないとやっぱわかんないですよね。
S:今って、DAWとPCとインターフェースがあれば誰でも始められるので、自分の作品を作るってなった時に、ちゃんとしたエンジニアさんやマイクプリなどのハードが揃ってるレコーディングスタジオに行く状況の方があまりないですよね。
もっと簡単にいうと最初から自分の技量と自分の持ってる機材でレコーディングをスタートする感じが一般的だから、今のお話に出てるところを飛ばしちゃってるというか。

D:うん、 2極化というか。後、やっぱり最初にある程度いいものを経験した方が伸びが早いんですよ。環境もそうで、いい環境を経験した方がやっぱりその後成長が早いというか。そういう意味では、別に無理して高い機材を買う必要はないですけど。なんかいいものに触れるとその分耳がよくなるみたいな感じはある。だから、せっかく何か買うんだったら「ある程度いいもの買った方がいいよ」と僕は薦めてます。
S:ですよね。どこの製品でもいいのでハードのコンプレッサーとかも、 1回は手にした方がいいと思ってます。
ハードで設定を探す感覚を見つけると、プラグインのかけ方がうまくなりますよね。プラグインのパラメータとかメーターだとね。 あんまり音に意識が行ってない気がしてて。で、ハードだと実際に触ってるからなのか、脳の中で数字じゃない何かに反応して触るので、そのポイントに気づくとプラグインの触り方のスイッチが切り替わる気がします。

D:うん。音の判断できるようになるっていうのはありますよね。もちろん手で動かせた方が直感的に作業できるよね。コンプとかもやっぱイン・アウトのバランスとかも重要だから。そこら辺も一度につまみで触れた方が早いよね。
Y:改めて思ったことがあって。先ほどのマイクプリの有無の話に戻るのですが、IF直の場合って、インプットメーターがしっかりありますよね。だから、Daichiさんがおっしゃっていた通りクリップしないようにとかの部分は分かりやすいですよね。けれどアウトボードって、そこまで正確な値が出てこないから耳に頼らざるを得ない。言い換えると、情報が少なすぎるから限られた情報というか「音」で判断するっていうところが結構やっぱ大事ってことですね。なるほど。もしかしたら上手くなる理由は多分そこなんだろうなと。
S:IF直だとメーター見え過ぎて、クリップしないってとこばっかり意識いっちゃってる気がするもんね。でも、それは基本というか入口で、その先が深く面白い。
Y:もう数字の世界じゃないぞって話ですよね。でもそれって、自分で体感して聞いてみないとだから、わからない世界じゃないかなと思ってきました。

D:例えば、ギターとかベースとか弾いてると、歪ませるとかも含めいいポイントで作ってたものって、最終の仕上げのところで差がしっかり出てくるんですよね。今って、後でなんとかできるようになっちゃったから、とりあえずで録っておいて、後で何とかしようって思えるけど、そこに対して言いたいのは、出来るっちゃ出来るけど結構色んなことやらないとゴールに辿りつかないってことかな。例えばボーカルだったら、後でちょっと歪ませたりすれば前に出すことはできるんですけど、結局それって元の素材に対してこう調味料をガンガン入れて味を作ってる感じになるかなと。
いろんなアナログ機材とか録音を熟知しているエンジニアだったら、録った素材に対して足りない要素をこのプラグインで補正しようとか、EQでここをカットすれば完成みたいに、その先のプロセスまでノウハウが蓄積されてるから出来るけど、やっぱり普通の人はそこまでわからないし完成まで持っていく難易度がとても高いと思う。

そういう意味では、技術がない人ほどハードに頼った方がゴールが早いと思います。なんで、こんなに全然抜けてこないんだろう?みたいのを EQとかでガシガシやって結果的に変な音になっちゃったみたいなことってよくあるよね。
Y:ありますね。
D:僕がハードを使ってる理由は割とそこで、僕も元々エンジニアじゃなくて、やっぱプレイヤーとか曲作ったりの方なんで。そういう意味ではやっぱりスタジオ経験ではエンジニアの人にはかなわないから、そこを穴埋めするというか。なるべく最短距離で答えにするに行くためにハード使ってるっていうのが、それが一番の理由なんです。
S:ギターを抜けさせたい曲だなと思ったら、まずAPIに手が伸びるとかそういう感じですよね。何もしてない状態から、ちょっと音抜けを作ろうってなると、すごい選択肢広いですもんね。IF直とか取りあえずの機材で録った後に何かで抜けさせようとするよりは、 最初からAPI通して録った方がもうゴールが見えてる。
で、そういうのがだんだん溜まってくるとどんどん作業も早くなるし、機材も増えてくるんでよね(笑)
D:うちはドラムとかも録るからどんどん機材が増えちゃったよね。
ITB(in the box)について
S:次にミックスするときにアウトボード使わない=ITB(in the box)についたお話を聞けたらなと。個人的な意見ですが、世の中のあのITBミックスの理解のされ方がちょっと誤解があるなと感じてまして。(レコーディングにアウトボードを使って録られてた素材なら)ミックスはプラグインでも行けるよっていう()の中の大前提があまり浸透してなく、プラグインだけでもいけるって言葉ばっかり目立ってる感じですよね。

D:うんうん。録る時に音作り込んであれば微調整で済むが正解で。俺も多少、語弊がある気がしてたから。たまに海外のあのマルチデータとかあの配ってるとかあるじゃないですか?割と有名なのとか。
で、やっぱあれとかって、データ並べただけでめっちゃいい音なんですよ(笑)結局、その後のMixで色付けどうのこうのじゃなくて、それぞれのトラックが素の状態でもういい音で、それを1つの作品にする作業というかとか空間を作る作業がミックスって感覚なんだよね。
基本的な音に関しては、素材を並べた時点で完成されてる。それが大前提のITBだよね。レコーディング時にとことん拘られてる素材のITBであって、それがやられてない段階でのITBは相当大変というかなかなか上手くいきにくい気はするよね。時間が掛ければ出来なくなくもないんだけど。ノウハウが無いととにかく大変。ミックスとかで結構苦労してる人ってそういうところもあると思う。
S:やはり素材の良さが結果につながり、それを突き詰めていくとハードを使う方が話しが早いってことですね!
下処理について
S:お仕事柄、その人の作業環境で録ったデータとかが来ることが多いと思うのですが、やっぱり何か下処理みたいなことはされますか?
D:この音はこの機種を通した方がいいないとかはやっぱありますよね。このままの音だとミックス時にああなっちゃうから、ちょっとだけハードで味を足してとかそういう使い方はありますよね。やっぱり結構それをやる人は多いと思うし、全CH SSLを通して録り直すみたいな事やったりもするよ。まあそれも含めて、クリエイターとしてのキャラクターというか。

S:僕の友人のクリエイターさんに、アレンジが決まったらハードシンセを全部Millenniaを通して、プリントしてからオーディオ編集する人がいます。ハード使うと、録音がリアルタイムなんでトラック数多いと時間が掛かるから、トラックが増える分Millenniaが増えてる感じでした(笑)でも全CHにMillenniaを通さないと、自分の音にならないみたいな拘りが素敵というか。
D:その辺はやっぱ個性というか、なんか物を作る時の感覚というか、いわゆるオリジナリティっていうのかな。そういうとこで個性を出すっていう意味でもあって、俺はこの機械めっちゃ好きだから何でもこれ通しちゃうみたいな。結局それだからこその仕上がりもあるし。後はシンプルにそれが楽しいから(笑)そういうのも、なんか仕上がりにも影響が出てくる感じがする。他人が分かるくらい変わらなかったとしても、その過程があるから楽しいよね。

Y:お話聞いてて思ったのが、そのさっきのマイクプリのインプットとアウトプットの関係とかその調整ってのがすべてそこに繋がるなって。その歪みとかコンプ的な役割とか。何かを通して仕上がりが良くなるって。本質はここですよね。
D:うん。結局そこのキャラクターがかっこいい音になるのが好き。結果的に歪んでるんだけどね。でも、それだからこそ最終的に抜けてくるし。ハードが評価されているのってそこだと思うんで。レコーディングで鉄板の組み合わせのU67&Neveの組み合わせなんかもう歪ませてナンボみたいな世界ですからね。
S:その後に1176までいっちゃいますからね(笑)
D:そうそう。で、その歪みの感じっていうのがプラグインだとまだハードに勝ててない部分。だからいつかそこができるプラグインとかができるかわかんないけど、ハードは結構最後まで残るんじゃないかなって気がしますよ。まあ、楽しみではあるんですけどね。ピアノとかギターとかのサンプルもかなりよくなったけど、やっぱり同時に音が鳴った時の共鳴とかっていうのって、結構難しいと思うんですよね。技術的な事は解らないけど、既に鳴ってる音があって、そこに別の音が入ってきた時にどういう風な変化をするかっていう時間軸の変化っていうのが、結構やっぱ一番難しい気がする。そういう意味ではフィジカルモデリングって進化してきてるけど、やっぱりまだサンプルの方が良かったりするし。
S: UAD-4くらいなら出来てそうですよね(笑)

Y:その時間軸っていうのも結構ポイントですね。さっきのIF直の時間軸って比較的固定だから出来上がりの先も固定なのかもって話ですよね。マイクプリとかの方が時間軸の変化にまだ揺らぎがあるというか。
冒頭に話した通り、いい意味でIF直は無難なんだけど、結局それだけでは深みがでないのかな。やっぱマイクプリはやっぱりいるってことですよね。ただ、まだ個人的な感覚だと使ってないプロの人も多い気もするんですよね〜。
S:実際に成功している系の人たちは、アウトボードをめちゃめちゃ持ってますよね。ポカロPとか歌ってみたの人とかも例外でなく。最初はPC1台で全部やってたってクリエイターも結局音質を追及していく、みんなこっち側の住人になってきますね。
揃える順番について
Y:Daichiさんがお仕事を始めたての頃って、当然多分予算も限られてくる話だと思うのですが、どこかのタイミングで一気に買ったのか順番に揃えて行った感じなんですか?
D:全然少しずつですよ。現在のスタジオの前の時は、家でやる事ってアコギ録ったりとかギターもラインで録ったりはしてましたけど、基本そのぐらいしかしてなかったんで。まだ外のレコーディングスタジオで作業する方が多かったですからね。ミックスはまだ自分でやってなかったし、だからプリのX73とコンプに1176があればとりあえずは録れたし。 マイクプリだったら、キャラクターが2つぐらいあった方がシーンに合わせて選べるからいいけど、もうそのくらいあれば充分じゃないかなって。特に数はいらないですね。
S:ですね。個人的にはまずは自分のパート分の1ch分揃えてみてほしいです。ボーカリストならボーカル、ギタリストのならその1chを自分で満足して録れるセットがあればいいと思います。



Y:今の人って昔と比べていろんな情報があるから、選択肢が多くて大変ですよね。
S:その山ほどある選択肢で悩んだらお店においで!俺たちと話そう(笑)
D:僕の時代だったら、10万円以内のギターとかは使い物にならないぐらいのクオリティだったけど、今ってもう全然充分でしょ。 安くてもいいものが多いんで、最初の取っ掛かりとして実際に使ってみて、そこからアップグレードしてけばいいよ。そして結局なんかずっと残ってるアウトボードは何かしらやっぱりいい理由があるのを忘れずに。
気に入ってるプラグインについて
S:今回のテーマに若干反するのですが、これだけハードがあったとしても、これはハードにできないなというか、気に入ってるプラグインとかありますか?
D:SOOTHE 2的なのってなかなかできないよね。同じ会社のSPIFFとかも。今まで耳で判断してたことを自動でやってくれる製品とかも増えたから。Auto-Align 2 でしたっけ。あれとんでもないですよね。全部自動で位相を合わせてくれるから。
S:ありがとうございます。その辺の必要だけど地味に時間が掛かる作業の効率アップにはプラグインの進化を感じますよね。
S:最後に僕がこの手の話すると結構言われるのが「結局、自己満じゃん?」っていうのがあって。でも自己が満足も出来てないものを人前に出すの?っていう。クリエイターとしてその姿勢どうなの的な変なこだわりありまして(苦笑)

D:まあ、機材とか自己満だとは思うんですけど。結局やる人のモチベーションが大事なんで、やっぱ信じるものは大事だと思うんですよね。僕は機材や楽器に関しては趣味ですと言っています(笑)好奇心や探究心が制作に直結する感覚があって、それが楽しいので。すごいお金かけてレコーディングスタジオ行ってこう高級な機材で録った作品と、スマホ1台、もうなんならマイクも使わず、スマホだけで全部やった作品でもTikTokでバズりましたみたいなことあるよね。どっちが偉いんだみたいな話になるけど、結局でもそれって実は別物だったりとかして。
曲とかもそうで、自分がいいと思った曲を作っていろんな人が聴いて、この曲いいねっていうのが増えたからファンが増えていく。それは多分、自分の好きなものを追及していった結果であって。それもそれでどっかのタイミングで当たる人もいれば。もうずっと当たらずの人もいるとか。 いい曲だけど売れなかった曲とかでも、それって作り手側として同じなんですよ。力抜いたから売れたかったわけではないもんね。ものづくりってそれこそ自己満足で追求して、結局それに共感してくれる人がどれだけいるかって話だけだと思うんです。
S:皆さんもどんどん自己満に追求して行きましょう!ありがとうございました。
まとめ

なかなかの長文になりましたが楽しんで頂けましたでしょうか?
アナログ機材を試してみようってなった人もまだ別にいいかなって人、どちらもいらっしゃると思います。もちろんやってるジャンルによっては無くてもいいものではありますし、種類も量も使い方も人それぞれです。正直、ハードウェアは機材も音源も面倒くさいです(笑)あからさまに音が違う的なアプローチもあるのですが、シンプルに何かに拘わるのって楽しいですよね?本文でも書きましたが、手で触ると人間はちゃんと反応し、結果に変わります。
音が良い状態で演奏すればプレイも良くなるし、プラグインだと触らないツマミやボタンも目の前にあるといろいろ触りたくなるんですよね。触ってみると想定してない音が出てきたりそんな機能あったのねってなったりもします。自分が楽しくて、その結果で人に伝わり方が変わって、良いリアクションが生まれるなんていう好循環が生まれるかもしれません!
まずはお店に来て体験してみませんか?今回の内容が少しでも実感頂ければ幸いです。
関連製品
マイクプリ
マイク
プラグイン
関連記事
記事内に掲載されている価格は 2025年9月25日 時点での価格となります。
最新記事ピックアップ