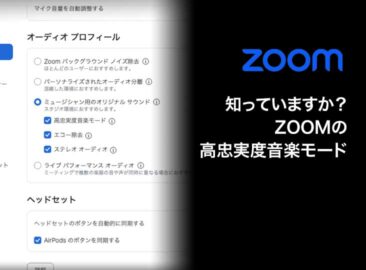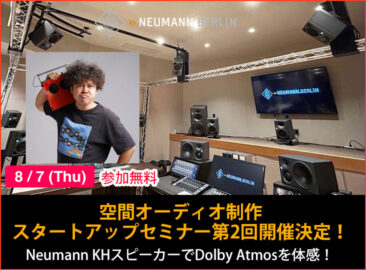HOTなクリエイターが求める最新情報をキャッチアップ。MUSIC・ART・文化、店舗情報まで盛り沢山

Next the 3rd Generation with Studio Parasight
Antelope Audio インターフェイスを導入決定したスタジオでは、なぜ Antelope Audio インターフェイスが使われているのかを徹底解剖!
Antelope Audio は第三世代のHDX対応インターフェイスとして、Orion32 HD | Gen 3、Goliath HD | Gen 3 を発表しました。現在のスタジオ事情として、HDX System対応インターフェイスの入れ替え時期に差し掛かり、HDX Portに対応したいくつかのサードパーティメーカーが発表しているインターフェイスの導入を考えているスタジオエンジニア、フリーランスエンジニアのためのイベントです。
Antelope Audioが提案するのは圧倒的な最先端のサウンドです。他のメーカーも非常に素晴らしい製品を発表していますが、この技術進歩が非常に速い昨今のデジタルオーディオ業界において、最新の技術を投入した第3世代の音質を体感してください。
スケジュール
1. 製品の紹介や技術紹介
2. スタジオエンジニアによる製品のインプレッション
3. 各インターフェイスで録音された音の比較
4. 実際のアウトプットの音質比較
5. 質疑応答
全体で2時間程度予定
参加者が持ち寄った2Mix音源もアウトプット可能。
| 日時 | 2019年10月4日(金) 18:00〜 |
| 場所 | Studio Parasight – A Studio(〒154-0015東京都世田谷区桜新町1-11-5) 地図 >> ご注意:駐車場はありませんのでお車でお越しの方は近くのコインパーキングをご利用ください。 |
| 定員 | 10名(先着順) 今回はHDX対応製品の試聴会となります。HDXを常日頃使用している方向けのイベントです。 |
| 視聴予定機器 |
Antelope Audio Orion32 HD | Gen 3 Antelope Audio Goliath HD | Gen 3 AVID HD I/O(比較用) |

Studio Parasight
Studio Parasightは14年ほど前にGrowing UPの自社スタジオをして作られ、Growing UPの所属アーティーストのレコーディングスタジオとして、Ellegarden,Stance Punks,No Regret Life,THE RODEO CARBURETTOR,UPLIFT SPICE,my way my love,BlieAN,Scars Borough, Nothing’s Carved In Stoneなどロックバンドをメインにレコーディングを行ってきました。
もともとのコンセプトがレンタルスタジオ使用を想定していなかったので、機材、デザイン、セッティングなど個性の強いスタジオです。
生音を忠実に再現することを第一に考えていたので、余計なパッチベイなどは無くし、回線の引き回しをシンプルにして音のロスを極力少なくするように考えています。
アナログ機材も個性的な機材を数多くそろえ、マイク類やコンプレッサーなどのアウトボードもバンド構成の同録を想定して揃えてあります。
デジタル機材に関しては、Mac + Pro Toolsというごく一般的なパターンにこだわらず、その時その時の一番気に入ったインターフェイス、ソフトウェアー、OS、マスタークロックを選ぶようにしてレコーディングしてきました。
最近スタジオの外貸し営業も始めましたので、気になる方はお問合わせください。(詳しくはホームページparasight.jpをご覧ください。)
2F – A Studio イベント会場

Console – Neve V3 Custom Build Console
Interface – Orion32 HD | Gen 3
Speakers – Musik RL900A



Engineer
西 秀男 (Hideo Nishi)
Chief Engineer
〜Career〜
studio Birdman, freelance, Think Sync Integral, DLB studio,GrowingUp,studio parasight
〜Works〜
織田哲郎,BOØWY,秋本奈緒美,亜蘭知子,村松健,清水宏次朗,B.B.クィーンズ,TUBE,L⇔R,The Stalin,Kenji Suzuki,Black Cats,山田淳,
遠藤ミチロウ,Gymnopedia,ROSY ROXY ROLLER,沢田知可子,西城秀樹,相川七瀬,Small Circle of Friends,チエ・カジウラ,高橋克典,
佐藤敦啓,The Gospellers,the margarines,THE ZIP GUNS,The gardens,kaleidoscope,THE TRANSFORMER,BAJI-R,COOL DRIVE,
Ellegarden,Stance Punks,No Regret Life,千万石,master*piece,THE RODEO CARBURETTOR,UPLIFT SPICE,The MUSMUS,JARNZΩ,
my way my love,BlieAN,RAT,CLUTCHO,Scars Borough,Brave Back,INKYMAP,Nothing’s Carved In Stone,uchuu;,福長美咲,and more…
エンジニアとしてのキャリアはもう35年を超えました、本当にいろんなアーティスト、いろんなジャンルの楽曲を手掛けました。
いまだに洋楽好きで、その年その年の今の音楽に浸り続けています。尊敬するアーティスト、エンジニアは多数すぎて絞れませんが、
目指す真実の音は少しだけ見えてきました。
その実現のため今はエンジニアだけでなくプロデュース、アレンジ、トラックメイク、ドラムチューニングなども手掛けています。
Antelopeの機材は現在、Orion32HD、OrionHD32 | Gen3とAMÁRIの3台を使用しています。
Orionについて
Orion32 HD | Gen3はA-Studio、Orion32 HDはB-Studio、AMÁRIはMixRoomに設置しています。
Orion32HDはレコーディング作業のインターフェイス、AMÁRIはMix、アレンジ作業のDAC兼モニターコントロールとして使用している感じです。
Orion32の一番の売りは1Uという大きさでかつ、標準でHDX経由でもUSB ASIO経由でも、32chIN/OUTが可能だという事です、スタジオの機材がいきなりコンパクトになりますし、DAWソフトウェアの選択肢が格段に広がるので、音作りの幅が大きく広がります。
Studioをレンタルする際にPro Tools HDを使うことが多いと思うのでOrion32 HDを導入しましたが、実際僕はPro Toolsは使用しないので、USB ASIO経由で使用しています、一台でどちらの選択肢も可能というのは非常にありがたいです。
Orion32 HD は2台共通してワイドレンジで透明感があり分離がよく歪が少ないいい音だと思いますが、音色が若干違います、Orion32 HDのほうがオーディオ的、Orion32 HD | Gen 3のほうがスタジオ的な印象です。スタジオ的というのはより情報量が多いというニュアンスです。
操作性はほぼ同じです。Antelope Launcherからコントロールパネルを立ち上げてルーティングやEffectを行えます。
ルーティングについてですが、良くできています、コンソールのパッチベイのようにアイデアのままに複雑なルーティングも可能です。ミキサーを複数内蔵しているので複数のアウトをミックスしてモニターのチャンネルに出力することも可能です。
レベル調整可能なステレオモニターのアウトプットが一系統ですがあるので、アクティブスピーカーにモニターアウトを直接つないでモニター回線を構築することも可能です。
実際Parasightではスモールモニターとラージモニターの切り替えや、モニターのDIMを頻繁に使う作業の時はAPIのモニターコントロールを使用していますが、MixやVoダビングとかは直接スピーカーにつないで作業しています、そのほうが淀みないクリーンなモニター環境で作業できます。
10Mクロックを受けることができるので、10MにロックかけておけばDAWのサンプリング周波数と違うサンプリング周波数のS/PDIFのデジタル入力をつないでもルーティングさえすれば、例えば1,2トラックはDAWのOUT、15,16トラックはS/PDIFの音をルーティングして出力するとかも可能で、実際重宝しています。
内蔵のプラグインについてですが、よく出来ています。録り込みの回線にルーティングしてしまえばレイテンシーを気にせずコンプEQの掛けどりが出来ます、正直なところコンプレッサーは操作性とかを考えるとアウトボードのアナログを使うことが多いですがEQは内蔵されているプラグインEQはキャラクターもうまく実機がモデリングされているので、十分使えます。
AMÁRIについて
Mix作業に使用しているAMÁRIについてですが、最大の売りはコンパクトさとそのルーティング能力でしょう。
正直Mixルーム的にはPCとAMÁRIとモニタースピーカーで完結です。各社似たコンセプトのデバイスを販売していますが、AMÁRIはAD/DAの音質で抜きん出ていると思います。Mastering Roomであの高価なMerging社のHAPIとAD/DAの音質を聞き比べましたが同じ10Mのクロックをつないだ状態では同等の高音質を確認できました。
AMÁRIも10Mクロックを受けることが出来るのでAMÁRIが持つUSB、AES、S/PDIFなどのデジタル入力に対してもデジタル同期は自由自在ですので、高音質なモニターコントロールとしても使えます。
フロント液晶タッチパネルでAMÁRI内部を自由自在にルーティングできるので一台完結を簡単に実現してくれます。
ルーティングだけでなく様々な設定や電源のオンオフなどもすべてフロントタッチパネルでアクセスできます。個人的にはAMÁRIは手元に置いて操作するのがいいと思います。
一つだけ残念なのが、2系統のアナログアウトがあるにも関わらずそれぞれの切り替えができないため、モニタースピーカーを複数つなぎたい場合は別途スピーカースイッチャーが必要になります、この点はAntelope社に改善を望みたいところです。
現時点ではレコーディングで使用していないですが、せっかく高音質のADですし内部レイテンシーも他のデバイスと比べて短くできるので機会があればVo録音とかで使用してみたいと思っています。
黒田 太郎 (Taro Kuroda)
Recording Engineer
Work Experience
DLB studio~GrowingUp~studio parasight
Works
ELLEGARDEN,Nothing’s Carved In Stone,MINAMI NiNe,Day6,UPLIFT SPICE,
The MUSMUS,The Rodeocarburettor,No Regret Life,Rat,Brave Back,Inkymap
Antelope Audio インターフェースの印象
以前使っていたインターフェースからの乗り換えでI/Oを探しているときに
Orion32 HDを視聴しました。原音に忠実でクリアな全体像で、音色に変な色付けが
なくレンジが広い印象をうけました。導入された後、実際のレコーディングで使用した感触も
録音再生ともに、最初にもったイメージのままの素晴らしいインタフェースだと思います。
今回Orion32 HD | Gen 3が新たに導入され使用してきた印象は、前のOrion32 HDの良さを減らすことなく
全体的にブラッシュアップされており、理想的な進化に感じました。
諸石 政興 (Masaoki Moroishi)
Mastering Engineer
1987年、オーストラリア・ブリスベン州生まれで、東京育ちです。
2010年よりコンピレーションアルバムを中心にマスタリング業務をスタートしました。その後、大量のお仕事を通じてマスタリングの面白さにのめり込むようになりました。
2017年には、デヴィッドボウイ・ジョンメイヤー・ノラジョーンズらを手掛けるSterlingSoundのグラミー賞エンジニア、グレッグカルビ氏より研修を受け、洋楽のアプローチを学ぶことができました。
2019年6月にParasight Masteringにマスタリングエンジニアに就任いたしました。
常に洋楽に負けないサウンドは何か、10年後も繰り返し聞いてもらえる音とは何かを日夜研究しております。
GOMESS / toitoitoi / Tepppei / Black Boboi / The Silent Service / 小林うてな / ermhoi / Julia Shortreed / ODOLA / 入江陽 / Japanese Folk Metal / uijin / A応P / and more…
Parasight Masteringはスタジオとしては以下の実績を持つスタジオです。
広々としたロビーとスタジオの居住性を兼ね備え、大人数の立会いにも対応しております。
セールスポイントとしては、ヨーロッパ機器を全て240vで稼働させていること、アナログケーブルはSterling Soundで採用されているReference Cablesで統一して採用していること、オリジナルの設計のクロックを導入していることになります。
新しい技術の登場を積極的に採用をしておりまして、新しい音を常に模索しております。
年々スタジオの姿が変わっていくのが一つの大きな特徴と言えるかもしれません。
お越しいただくたびに、きっと、何か新しい発見をしていただけることでしょう。
AMÁRI批評
Parasight Masteringでは、AMÁRIを採用しています。
以前からマスタリングスタジオの定番コンバーターのEclipse384を愛用をしていたのですが、そこからAMÁRIに乗り換えたのには理由があります。
1、サウンドステージの広さ
Antelopeオーディオの特徴として、広いサウンドステージを持ったサウンドを奏でてくれることがあります。クロックの特徴でもあり、コンバーター自体の特徴でもあるように感じます。
AMÁRIは過去のAntelope製品の中で、最も広いサウンドステージを持っており、他のコンバーターと比べると、まるでホール席から演奏風景を見渡しているような雄大さを感じさせます。そして何より、eclipse384よりもクリーンであり、ワイドであり、低歪です。
2、サウンドの甘さ
コンバーターは色々な種類のサウンドを持っています。どれもリファレンスグレードを謳っているものの、それぞれが思うリファレンスグレードになるので、皮肉にも、そう謳っている製品ほど各メーカーの思想が反映される結果になっています。ではAMÁRIはどうでしょうか?
AMÁRIはデジタル的な精緻さを継承しつつも、聴きやすい甘さを兼ね備えています。
甘さというのは、耳につきやすい帯域のトランジェントの丸さです。
例えば他のコンバーターでディエッサーが必要なときにAMÁRIを使うことで余計なプロセスを回避することができる程度に、耳に刺さる帯域について丁寧に作られている印象です。
3、ADコンバーターの優秀さ
ほとんどの人がAMÁRIをDACとして利用しようとするものと予想をしますが、インプット、つまりADコンバーターはどうでしょうか?
DAと同じくスッキリした印象で、やはりワイドに音を受けてくれます。しかしながら、余計な味付けを感じることはありません。非常に真面目に作られている印象です。
トランジェントについても、やはり痛くなりがちなポイントをうまくゆるく受けてくれる印象ですが、かといってスピード感が落ちるということもなく、うまく受けてくれます。
他にもHapi,QES,Burlといったコンバーターを使っているのですが、その意味ではAMÁRIは最も中庸な印象です。
総評として、言えることは、AD/DAの性能は単体機と比べても全く遜色ない仕上がりということです。
この価格帯で発売されていることが俄かに信じがたいです。
特に、Orion 32 HD gen2もそうなのですが、Antelopeのサウンドは頭一つ抜けた印象があり、その流れの中にAMÁRIは先端に位置している印象です。
イベントに関するお問い合わせは Antelope Audio まで。
StudioParasight 設備紹介
1F – B Studio



3F – Mastering Room



Mix Room



Photos: Naruki Konagaya
記事内に掲載されている価格は 2019年9月13日 時点での価格となります。
最新記事ピックアップ