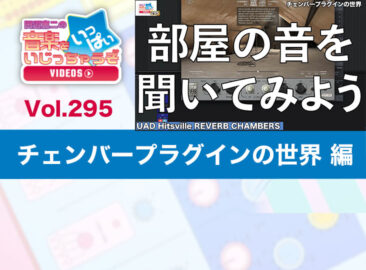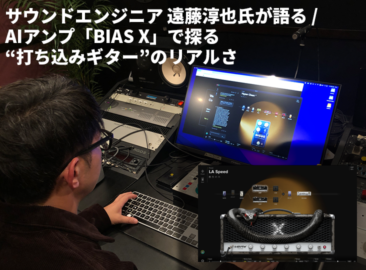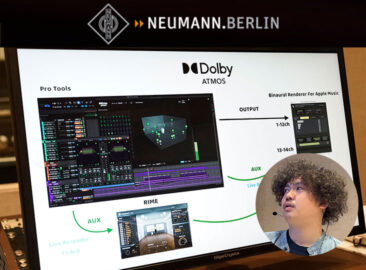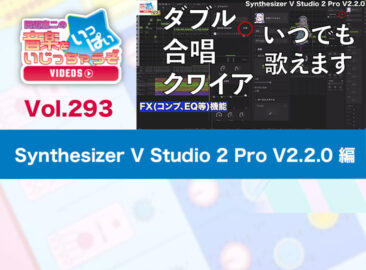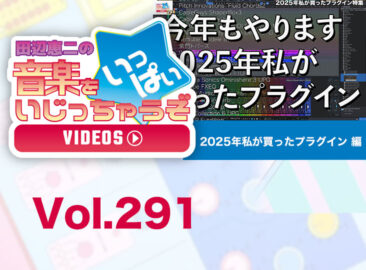あなたの楽曲制作にヒントをもたらす数々のノウハウ記事に加え、膨大な動画コンテンツは制作トレンド&Tipsの集大成!

ソフトウェアミキサーアップデート

これまでのSymphony Controlでもモニタープリセットが3つまでセット出来ていましたが、今回この自由度が飛躍的に向上。
Symphonyの最大物理出力は16×16カードを2枚備えた場合の32chになりますが、この32chをMonitor Workflowを使って最大まで活用することが可能になりました。
Monitor Workflowは3つのモニタープリセットに囚われず、32chを自在にルーティングできます。
例えば、ひとつのスタジオで16×16のSymphony I/O MkIIがあるとして…
A日: dolby atmos(7.1.4ch)=12ch
B日: Sony 360(13.0ch)=13ch
C日: ステレオ作業、モニター2ch+キューアウト+アウトボード =2ch+α
なんとも楽しそうなスタジオですが、最大で12ch以上をコントロールしなければいけないハードな環境でも、Symphonyはモニターコントロールがワンタッチで切り替え可能です!日ごとにどのような使い方があるのか、見て行きましょう。
A日: Dolby Atmos(7.1.4ch)=12ch

通常のステレオ対応のI/Oでは、ボリュームを上げてもLRの2chしか上がらないので、Dolby Atmosのモニターコントロールは12chを同時にコントロールする必要があります。
今回空間オーディオに対応した事で、アナログ12アウトを外部のモニターコントローラー無しで一括コントロール可能になりました。
いよいよDAWにもDolby Atmosレンダラーが標準搭載されてきた昨今、インターフェース側の早急な対応が求められるところですが、まだまだ実現しているブランドは少ないのでSymphony Controlは先進的な機能と言えます。
B日: Sony 360(13.0ch)=13ch
こちらも技術的なところはSymphony Controlで賄えるものですが、他社や従来のSymphonyでは一手間必要だったところも最大32chの出力コントロールができるSymphony Controlでは全く問題ございません。
仕込んだ後は”B”とラベリングしたボタンを押すだけでコントロールが可能になりますし、もちろんA日のセットにもボタン1発で戻ります。
加えて、各スピーカーのボリューム微調整に使えるスピーカーレベルトリム、LFEだけミュートするなどが簡単に行えるMUTE/SOLOボタンも各チャンネルに備えており、従来はGrace Design / m908などのハイエンドモニコンを導入しないと実現しなかった機能が、本体タッチパネルもしくはわずか数万円のApogee Controlで操作できるとなれば、トータルコストも抑えられ比較的リーズナブルに大規模なスタジオシステムが構築できます。

C日: ステレオ作業、モニター2ch+キューアウト+アウトボード =2ch+α
ステレオのスタジオで、モニターはニアフィールド+1ペアという場合、残りの回線はアウトボードやキューミックスにルーティングという場合でも、最大16個のMonitor Workflowを作成できるSymphony Controlならデジタルパッチベイ的な使い方も楽々行えます。
空間オーディオはやらない!ステレオしか作業しない!という方でもモニタープリセット機能は腐りません。物理的なケーブルの抜き差しを最小限に、録音/ミックス/マスタリングという風に3つのセットを組むことが可能です。
マスタリンググレードのAD/DAコンバーター搭載のApogeeなら、ラウンドトリップの音色変化も最小限に、お手持ちのアウトボード群もさらなる活躍が見込めることでしょう。
さらにデュアルモノ系のプロセッサーを録音ではボーカルに1chだけ、ミックスではソフトウェアシンセにステレオで掛けたいなどの場合も、余計な色付けを行わずSymphonyを介したままとても柔軟にルーティングを組むことが出来ます。
アナログパッチベイで不要な接点を増やさず、当日のトラブルにも見舞われにくく、またデジタルパッチベイの機能をI/Oの機能(symphonyユーザーは無償)として享受できるのはお得ですね!
Monitor Workflowっていわゆるグループでしょ?
モニター組みは他のI/Oでもできますやん、となったそこのあなた、Symphonyにはまだまだポテンシャルがございます。
他社インターフェースでは7.1.4の個別 MUTE / SOLO の切り替えはワンアクションで出来る製品はまだ少なく、モニコンの追加投資無しでこれが行えることはやはりアドバンテージ。
これに加えて、入力ソースはインプットTHRUとプレイバックの切り替えが可能ですので、リスニング用途でSymphony I/Oをご愛好されているユーザー様にもHDMI→AVアンプ→アナログ12chという空間オーディオのホームシアター用途の時にSymphony I/Oを介していただければ、個別モニターやそれぞれの機能がご利用いただけますし、メディアとNetflixなどのWebコンテンツを切り替えるコンバーターとしても大活躍します。
ところでDSPは入っているの?
モニター補正のDSPが入っているかどうかですが、こちらは残念ながら未実装でございます。
音質の追求に販売価格の全てを注いだApogeeでは、足りない部分は別で用意してくれ、というスタンスでございます。
ちなみにSymphony I/Oの中にはオーディオルーティングやファームウェアアップデートで動く小さなコンピューターとしてFPGAが入っています。
SymphonyにDSPが必要な方、というのはやはり空間オーディオに携わる方々。各スピーカーのEQとディレイ補正は人力では限界があるのでどうしても必須です。
Rock oNからお勧めしている追加装備としては、Apogeeパートナーを務めるGinger Audio / Ground Control Sphereというプラグインです。https://gingeraudio.com/groundcontrol-sphere/
残念ながら国内に代理店が無く、本国から直接ゲットするという購入難易度になりますが、こちらのプラグインにてEQ処理、ディレイ設定と、さらにSonarworksの測定データを読み込める機能がありますので、これで音響補正周りはハードウェア/ソフトウェア共にパーフェクトになります。
新しくなったI/Oカード、拡張モジュール類

2x6SE (Special Edition)
Special Editionの名のとおり、これまたApogeeが音質に全てを注いだ2in6outモジュール。
こちらは従来からラインナップされているカードですが、今回どちらかと言うと他のカード(16×16)が2x6SEに追従する形でseに切り替わっていますので、その元になったモデルになります。
AD/DAはESS社の最上級を採用、第3世代になって更なるダイナミックレンジとSPLを獲得し、最初のカードとしては申し分ない仕様の定番カードになります。

Connect 8×8 MP
8×8は従来からラインナップにありましたが、1つのD-SubコネクタでMIC/LINEの切り替えが可能となりました。これでもうラックの裏にダイブする必要はありません。
2x6SEと同様、AES/EBU以外のデジタル入出力が付属しますので、S/PDIFデジタル入出力が必要な場合は2x6SEかこちらのカードが必要になります。
Roc oNでご提案させていただく時に多い組み合わせがこちらのConnect8x8 MPに16x16SEでアナログ24×24(マイクプリも8ch!)+デジタルADAT, S/PDIF, AES/EBUを網羅したシステムです。

16 x 16SE
2×6であったSpecial Editionが16×16にも適用され新しくなりました。2x6SEと同じマスタリンググレードのスペックを持ち、これはConnect 8x8MPとも差別化されておりますし、このカードを2枚で構成するとわずか2Uの筐体に64ch(32×32)のモンスターi/oが爆誕します。
代理店に色々聞いてみた
Q:Symphony Controlの機能ってThunderbolt版だけの話ですよね?PTHDやDanteで繋いだ場合はソフトウェアミキサーのスピーカーコントロールはできますか?
A: Symphony Controlの機能となりますので、ソフトウェアに統合されています。PTHDやDanteでは使用できません。
Q: ぶっちゃけ10年選手ですが、どうっすか?音は今でも最高峰ですか?
A: Symphony Mk2はマスタリンググレードのSymphony Mk1からADDAをさらにブラッシュアップしたモデルですので、音には絶対の自信があります。既存のユーザー様へは、特に新型のSEカードは高い評価を頂けておりますので、オススメです。
Q: Windowsで使用することはできますか?
A: できません。ただしDanteカードのオプションがあるので、Danteで接続すればDante機器としてネットワークにAD/DAを追加する事は可能です。
Q: MkIIIは出てきますか?
A: その予定はまだありません。
Q: Thunderbolt2規格のままですが、Thunderbolt3や4に、時代の流れにUSB Type-Cになったりしますか?
A: その予定はまだありません。
1985年創業依頼一貫して硬派なApogeeですが、マスタークロックも製造できる技術力を持つブランドですので音への妥協は一切無し!でございます。
今回ソフトウェアのアップデートも非常に便利なものとなっていますので、Native環境でクラス最高峰のインターフェースをお探しの方は是非Apogeeをご検討ください!
Apogeeについて深く知るSymphony I/O MKII 製品ラインナップ
記事内に掲載されている価格は 2024年4月23日 時点での価格となります。
最新記事ピックアップ