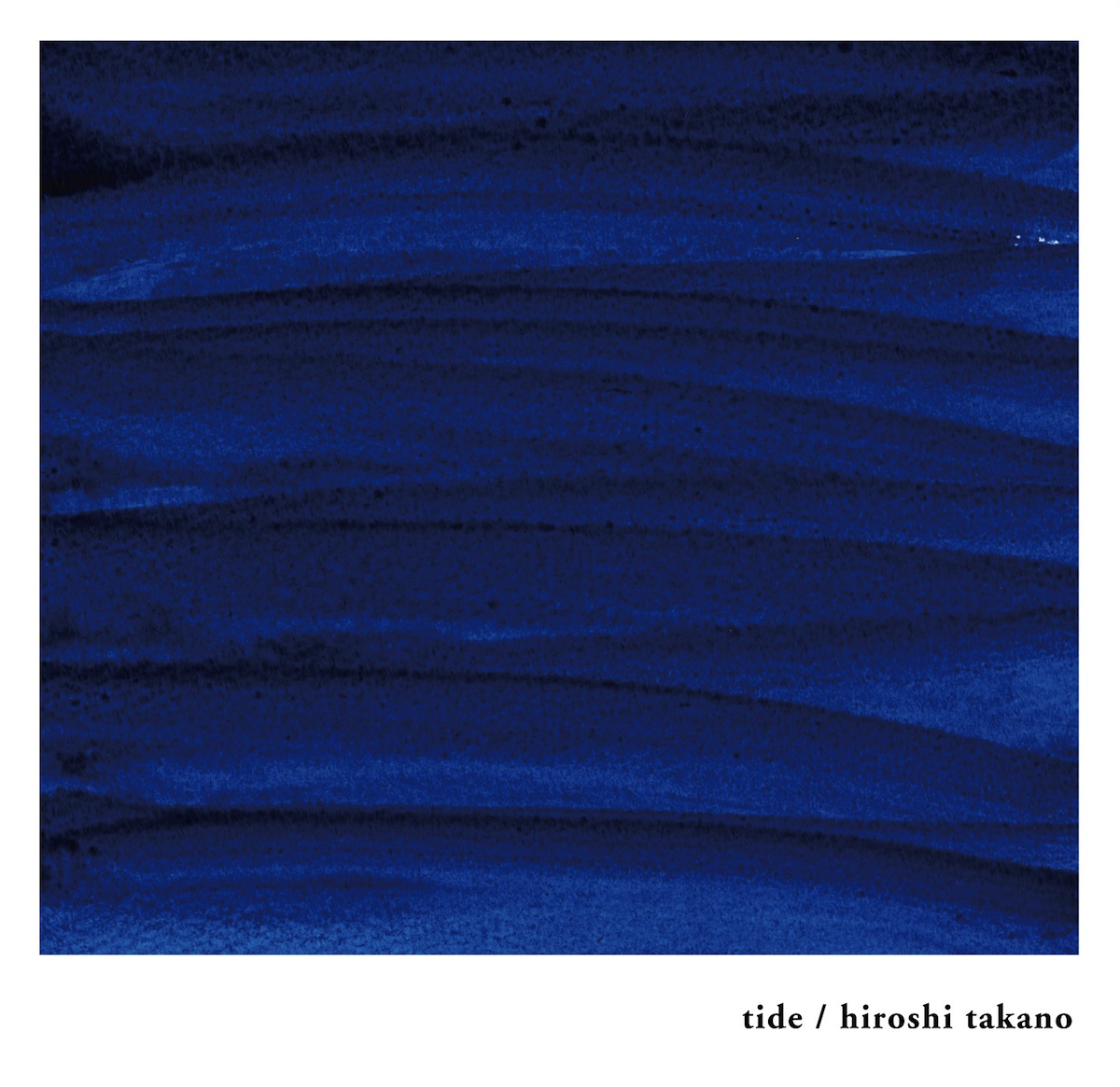音をクリエイトし、活躍している人をご紹介するコーナー「People of Sound」。このコーナーでは、制作者の人柄が、サウンドにどうつながっていくのかに注目。機材中心のレポートから少し離れ、楽しんでお読み下さい。
第30回目はミュージシャンの高野寛さんです。ご自身のソロアーティスト活動はもちろんのこと、pupa を始め、幅広く活躍されている高野寛さん。ちょうど取材した10月からデビュー25 周年のアニバーサリー期間に入られるということで、このグッドタイミングにお話をお伺いしました。音楽的生い立ちからデビュー秘話、トッド・ラングレンとの出会いなど、高野さんが歩んで来た25年、そしてこれからへの展望を含め、高野さんのミュージシャンとしての真摯な姿に迫りました。
2013年10月8日取材
音楽人生へ方向付けたYMO との出会い
Rock oN:この度はお時間頂きましてありがとうございます!高野さんの幼少の頃から時系列にお話をお伺いし、高野さんが音楽とどう関わって育ち、今の音楽人生に繋がってきたか、お話を聞かせて頂ければと思います。まず、音楽に触れられた頃のお話をお伺いできますか?
高野寛氏(以下 高野):父親が新しもの好きで、家にはポータブル・レコードプレーヤーや、当時まだ珍しかったカセットレコーダーがありました。幼稚園から小学校上がりたての頃に、それを使って録音することを子供の遊びとして始め、テレビの主題歌を録音してました。最初はマイクをテレビに向けて録音してたんですが、兄貴が騒いだりして余計な音が入るので「どうしよう?」と考え、イヤフォンジャック経由でライン録りすることに気付きました。
Rock oN:小学1,2年生でライン録りに気付くって結構早いですね。ご家庭で音楽は流れてました?高野:そうでもないです。親が歌番組好きだったので歌謡曲はたくさん聞いてましたが、家にあった何枚かのレコードやソノシート、それにテレビの主題歌程度です。その中で印象に残ってるのはジャングル大帝なんですが富田勲さんが手がけられていて、「他の曲と質感が違う」と子供ながらに感じてました。幼稚園の時に1年間だけオルガン教室に通いましたが、実技の練習が好きじゃなくバイエル1冊も終える事なく通うのを辞めました。でも三和音の聞き取りだけは絶対間違えない子供だったんですよ。父はいわゆる転勤族で、神奈川を始め、静岡県内でも3カ所も引っ越して転々としました。当時は今と違って東京と地方の情報格差がかなり大きく、民放TV局は1局、FMもNHK1局だけというような状況だったので、大人になって東京生まれの同年代と話すと、育った環境がぜんぜん違うんですよ(笑)。
Rock oN:ミュージシャンにとって、育った環境がもたらす影響は想像以上に大きいですよね。ギターを始めたのはいつですか?高野:中学1年生の時です。兄貴が遠くの楽器屋まで足を運び、フォークギターを買って来ました。最初は兄貴が上手かったんですが、次第に、僕が知らない曲でも耳でコードを採れるようになり追い越しました。それと並行して「学研の科学」が好きな子供で電気工作にもはまってました。「シンセサイザーって面白そうだな」と思う時期があって、富田勲さんのLP「バミューダ・トライアングル」を買ったんです。僕が初めて買ったLP は、かぐや姫のベスト盤と「バミューダ・トライアングル」で、フォークブームと電気工作への2つの興味を表していて、フォークギターで音楽そのものに触れながら、同時にシンセのようなテクノロジーにも興味を持っているという、僕の分かるようで分かりにくい指向を表してる気がするんです。
Rock oN:のちに大阪芸術大学に進まれますが、アートに触れる環境はあったんですか?高野:いえ、アート方面に携わる親族もいないし、そういう環境では全然なかったです。僕がアートみたいなことに目覚めるのはYMOです。ラジオでYMO のツアーをやってるのを聞いたんですが、演奏にシーケンスが使われてるのがとても新鮮でした。高校入学前の春休みに「ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー」を聞き、そこからどんどんはまって、以降、リアルタイムでYMO の新譜を買って行きました。坂本龍一さんのFM番組「サウンドストリート」を始めとして、色んな音楽を耳にして影響を受けるようになり、「音響系の大学に進みたいな」と思い、大阪芸大の芸術計画学科 音響コースに進みました。
Rock oN:YMO のライブですが、ラジオ越しに聞いても、背景に機械が使われてると感じ取ってたんですね?高野:そうですね。それを聞いたらシンセサイザーが欲しくてたまらなくなりました。でもその頃は、シンセはおろかエレキギターも買えない年頃なので、自分でスピーカーからコイルを外してピックアップを自作して、それをフォークギターにくっつけてエレキ化したんです(笑)。そんなことばかりやってました。高校入学時に、親が何か楽器を買ってくれるということになり、僕は何を買ってもらおうかすごく悩んで、本当はシンセが欲しかったんですが、ローランドSH-2 が10万円くらいして、「10万出してモノフォニックじゃ何も出来ないな」と思い、家にはオルガンがあったので、ギターとベースを買ってもらうことに決めました。
高野さんの世代のミュージシャン、特に自宅録音に夢中になっていた少年や青年に大きな影響を与えたのがYMOの存在でしょう。現在活躍する多くのミュージシャンの口から、YMOの存在の大きさについて言及されることが多々あります。男の子が夢中になる「メカ」や「工作」。音楽と同時にその部分を刺激してたことも大きな理由ではないでしょうか? 現在、YMOの三方と多いに関係する高野さんですが、そんな高野さんのデビューにYMOのメンバーが大きく関係してたというお話が続きます。
自作シンドラと電子メトロノームで作られた最初の多重録音作品
Rock oN:一人で作品を作ろうという買い方ですね。当時からマルチプレーヤー志向があったんですね?高野:僕のギターヒーローはエイドリアン・ブリューやアンディー・サマーズなので、ソロを弾きまくるようなギターヒーローに憧れたこともないし、実は、シンガーになろうと思ったこともないんですよ。
 Rock oN:確かに典型的なギターヒーローとは違いますね。バンドはやりました?
Rock oN:確かに典型的なギターヒーローとは違いますね。バンドはやりました?
高野:バンド活動は高校の時に始めて、最初はベースでした。機材の面でYMOの曲を演奏するのは難しくて、YMOがツアー時に演っていた矢野顕子さんの「在広東少年」を女の子のボーカルで演ってみたり、当時の流行でフュージョンやハードロックなども演りました。バンドでは自分の本当に演りたい音楽と少し違い、満足できない部分があったので17歳の時に宅録を始めたのですが、最初はウォークマンとラジカセを使ってピンポン録音してました。また、雑誌の自作記事を見てシンセドラムを作ったり、当時、NHKでやってた電子工作の番組を見て電子メトロノームを作り、その電子メトロノームをトリガーにしてシンセドラムをピンポンして作ったのが僕のファースト多重録音作品です。総額8千円程度ですね(笑)。
Rock oN:すごいですね。シンセドラムは最初から音は出ました?高野:出ましたよ。ノイズまじりだけど(笑)。その後は、カシオトーンのリズムに合わせてベースとギターを重ねたり、フォークギターとベースを使ってYMOの「中国女」を多重録音したり。
Rock oN:その時点で歌うことはなかったんですか?高野:歌は、高3の時にバンドのボーカルが受験勉強で抜けたので、代りに歌い始めたのがきっかけです。当時やってたヤマハ ライトミュージックコンテストなどに作品を応募したんですが、最初のテープ審査にもひっかからない結果でした。デビューするまで色んなオーディションに送ったんですが、だいたい「歌が下手だ」ということを言われましたよ(笑)。
Rock oN:シンガーになりたいということじゃなかったんですよね?高野:そうなんですが、音楽自体は歌ものが好きだったので、作る曲の半分以上は歌ものでした。大学時代に最後にやっていたバンドが解散したすぐ後に、高橋幸宏さんと鈴木慶一さんのテントレーベルのオーディションがあり、テープを送ったんですが、そこで初めて高い評価をもらったんです。
Rock oN:そのデビューのきかっけになったオーディションの曲は、以前、テレビの番組で流されたのを聞きました。ギターカッティングが前に出た、パッキパキのニューウェーブな感じでかっこよかったです。高野:応募した曲は、1曲は変拍子のインストで、そのテレビで流した曲は歌ものだったんですよ。
Rock oN:ご自身のやりたい音楽の方向性が、かっちり決まっている印象でした。高野:そうですね。だいぶ出来上がってたと思います。ざっくり言えば、テクノ、ニューウェーブの影響が大きかったんですけど、ビートルズ、YMOから始まり、その周辺の音楽、そして大学の頃からトッド・ラングレンをたくさん聞くようになり、他にプログレも好きだったし、それらの色んな音楽が絡み合って自分の音楽の核になってますね。もっと言えば、小さい頃聞いていたフォークや歌謡曲も自分の根っこにあって、歌詞カードを見なくても歌で伝わる曲、口ずさみやすいメロディーがある曲、というのが自分の奥底で基準になってると思います。イントロやオブリのフレーズ作りでも、口ずさめる歌メロの延長上にあるか、ということが重要な基準になってます。
デビューのきっかけになるオーディション。続くYMO との縁。
 Rock oN:テントレーベルのオーディションはどういう内容だったんですか?
Rock oN:テントレーベルのオーディションはどういう内容だったんですか?
高野:ちょっと変わっていて、「究極のバンドオーディション」という名前だったんですが、各パートを募集して合格者でバンドを作る、というコンセプトでした。合格者には僕と、ベースの男性、女性ボーカル、あと、後にm.c.A・T になる富樫明生君がいたんですよ。最初は、僕と富樫君とベースの人でバンドを組む計画があったんですがそれは流れて、その次は僕とベースの人と女性ボーカルの組み合わせの案が出ました。それもデモを3曲録って終わっちゃったんですが。
Rock oN:応募した高野さんのテープは何が評価されたんでしょうか?高野:高橋幸宏さんがよく言ってたのは、僕の健康的でさわやかな写真と、出てくる音楽のギャップが面白かったらしいです。「歌のお兄さんのような写真の青年がひねくれた音楽を演ってたら面白いよね」と言って聞いたらまさにそんな感じの音楽で、「そこがはまった」と言ってました。その後、高橋幸宏さん、鈴木慶一さんのザ・ビートニクスのツアーにギターとコーラスで声をかけてもらいました。もう一人のギターが大村憲司さんで、僕は当時、エフェクターを使った特殊奏法が好きで、自分で改造したギターを使ってたんですが、今思えばひどい音で(笑)、横で大村憲司さんが弾いてるのを見ると、エフェクターも3つくらいしか使ってなくて、それでもものすごくいい音なんです。「なんだろう、この違いは!?」と思って「エレキギターは弾くのをしばらくやめよう」と思ったくらいショックでした。
Rock oN:その時、おいくつだったんですか?高野:21歳ですね。譜面の見方も全然分らないし、「プロは1日8時間もリハーサルするんだ!」とびっくりしたし(笑)。
Rock oN:(笑)。でも高橋幸宏さんが高野さんをギタリストとして抜擢した理由があったんですよね?高野:面白がってもらえたんだろうし、カッティング系は僕がやるということと、大村憲司さんはアコギを弾かない人だったので、アコギのパートとコーラスを僕がやる、ということもあったし。そのツアーは7、8本まわって、「夜のヒットスタジオ」にも出れたし、色んな現場を勉強させてもらいました。
 Rock oN:まだ大学生だったんですよね? そのツアー経験で自分の進む道が見えてきましたか?
Rock oN:まだ大学生だったんですよね? そのツアー経験で自分の進む道が見えてきましたか?
高野:う〜ん、オーディションの時点では、今の自分に繋がるような自作曲はそんなに出来てなかったので「アコギの弾き語りができる人にちゃんとなろう」と決心しました。時期的にテクノ、ニューウェーブの波が落ち着き、60年代、70年代の音楽を再解釈するようなムードに入っていました。XTCの「スカイラーキング」やジョージハリスンの「クラウド・ナイン」、ビートニクスの「EXITENTIALIST A GO GO」がそういうテイストを持っていて、今までの自分の流れに照らし合わせ、しっくりくる所だったので、アコギをメインにして作曲を初め、オーディション後からデビューまでの2年間、たくさん曲を作りました。
Rock oN:1st アルバム「hullo hulloa」は、その期間に書いた曲が入ってるということですか?高野:そうです。当時、まず、担当ディレクターにデモを聞いてもらってアドバイスをもらい、最初は1ヶ月に2、3 曲しか作れなかったんですが、次第にもっと作れるようになっていきました。ただ、弾き語りだけだと鑑賞に堪えられる感じじゃなかったので、しっかり他のパートも宅録で作りました。その頃は、シーケンサーのローランド MC-500、4オペレーターのマルチ音源モジュール ヤマハFB-01、デジタルシンセのカシオCZ-101、リズムマシンはローランド TB-909 を使ってました。大学生としてはそこそこな機材だったと思います。
発明家への夢がもたらしたオリジナリティへの執着とは?
高野:その頃は将来の職業として、シンセサイザーの設計もしてみたいなと考えていたんですが、数学と物理が苦手で。でも、自作楽器を作るにあたって、パネルのデザインはすごく得意だったので、楽器デザイナーみたいな仕事はできないかな、と思ってました。そんな考えを持ちつつも、作曲を続けるうちに、音楽を作る方にどんどん夢中になっていきました。小学生の時の夢は発明家になることだったんです。発明をするという事に今でもこだわりがあって、子供の頃描いていたのはハードウェアの発明家ですが、今は、それを音楽に置き換え、音楽も発明になりうるんじゃないかと考えてます。オリジナリティということに対して、すごく執着が強いですね。
Rock oN:もっとその辺り、お聞かせください。高野:デビューの頃は、いわゆる渋谷系の時期とかぶり、知り合いも沢山いましたが、僕がそっちに入らなかったのは、ネタをサンプリングして再構築するというムーブメントに対して自分で納得いかなくて、本当はオリジナルなんて無いのかもしれませんが、「ネタ」という言い方に抵抗を覚えてて、どうしても「オリジナリティ」ということに執着する気持ちがあったからだと思います。もちろんネタありきの音楽自体が嫌いだったわけじゃなく、たとえばディー・ライトも大好きだったんですが、自分で音楽を作る際は、そっちではないという意味ですね。サンプラーも買って試しましたが、スタートポイント探して切ったり、「ネタ」をチョップしたりとか、そういう作業がなぜか苦手で、上手く使えなかったです。
Rock oN:なるほど。シンガーソングライター気質が中心にあるということでしょうか?高野:そうかもしれません。後に出会うトッド・ラングレンがよく言ってたことがあって、「作品のプライオリティーのピラミッドがあり、一番上に来るべきなのは歌詞とメロディー、その次がアレンジ、そしてサウンドはその下だ」と言うんですよ。それは、まさしくソングライターの価値基準だと思いますが、僕もその考えにすごく共感するし、そこを大事にしたいという気持ちが強いです。
 Rock oN:デビューされた頃のお話をさらにお聞きしたいのですが、曲を作りためた期間を経て、デビューはすんなり決まったんですか?
Rock oN:デビューされた頃のお話をさらにお聞きしたいのですが、曲を作りためた期間を経て、デビューはすんなり決まったんですか?
高野:若干ですが紆余曲折あって、さっき話した「究極のバンドオーディション」はポニーキャニオンの企画でしたが、テントレーベルから高橋幸宏さんが抜けることになって、オーディションの合格者でバンドを結成する話もなくなってしまいました。僕も一旦宙ぶらりんな状態になったんですが、幸宏さんの事務所に入ることになり、幸宏さんプロデュースでソロシンガーとして東芝EMIからデビューすることになりました。その辺は、大人の事情で色々あったと思いますが、僕はただひたすら曲を作ってただけです。オーディションから考えると、曲を作りながらデビューを待ってる時間は長かったんですが、メーカーがプロモーション戦略を考えてる期間も含まれていて、東芝EMIからデビューすると決まったら、割とすんなり進みました。
Rock oN:大学卒業されて、その年の秋にデビューということですね?高野:そうです。だから、普通のバンドマンが通るような下積み時代がなく、フロントのシンガーとしてライブを引っ張ったことがなかった人間がいきなりデビューすることになったので結構大変でした。まして、デビューアルバムに参加して頂いたメンバーは、幸宏さん(ドラム)と小原礼さん(ベース)、大村憲司さん(ギター)、小林武史さん(キーボード)ですから、緊張したという記憶しかないです(笑)。
Rock oN:デビューアルバムのレコーディングの思い出はありますか?高野:スタジオはEMIの3スタとstudio TERRAでしたが、大きなスタジオでレコーディングした経験がなかったので、最初、ヘッドフォンの音量調節がよくわからなかったんです。歌を録っていて「どうしてこんなに音程が合わないんだろう?」と思ってたら、ヘッドフォンの音量を上げすぎていてピッチがシャープして聞こえてたんです。
Rock oN:サウンドの方はどうだったですか?高野:僕がMC-500で作ったMIDI データをマニピュレーターのNEC PC-98/カモンミュージックにコンバートして、Prophet-5やFairlightを鳴らすんですが、僕が宅録で作り上げていたサウンドのイメージは、カセットのテープコンプが強力にかかっている音で、スタジオのハイファイな音とだいぶ違ったんです。エンジニアさんに「コンプかけて下さい」としつこく言ってました。当時、レコーダーは32トラックのMITSUBISHI プロデジだったかな?
Rock oN:最初のレコーディングで、そのギャップは仕方ないですよね?高野:そうなんです。ラージモニターで鳴らすだけで全然イメージが違うし、ヤマハ NS-10Mも癖があるし。それで、イメージの擦り合わせがなかなか出来なくて、腑に落ちない部分もあったりしたんですよ。
YMOと同様、高野さんの作品でキーワードになる人物がトッド・ラングレン。先日、日本でも刊行された書籍「トッド・ラングレンのスタジオ黄金狂時代 魔法使いの創作技術(スペースシャワーネットワーク)」にも書かれてる通り、アーティストとしてはもちろんのこと、プロデューサーとしても長いキャリアを築く存在であることは周知の通りですが、スタジオワークを共にした高野さんからトッドの実際の人間像について伺ってみました。
スペシャルサンクス表記が繋いだ不思議な巡り合わせ
Rock oN:3rd アルバム「CUE」のプロデュースがトッド・ラングレンになったきっかけは何だったんですか?高野:不思議な巡り合わせがあって、もともと僕は彼の大ファンで、ファーストアルバムのSpecial Thanks欄に、勝手にトッド・ラングレンの名前を表記したんです。その直後くらいに、トッドのマネージメント会社から日本のレコードメーカーに「今、日本のアーティストに興味があるから、めぼしいアーティストのデモを送ってくれ」といったFAX が来たんです。それで僕のディレクターが「高野君、トッド・ラングレン大好きだから送ってみたらいいんじゃない?」ということになり、音源を送ったんです。そしたら、わりとすぐに返事が来て、「今作ってるデモも聞かせてくれ」ということになって、デモを送ったんです。そしたら、「やろう」という返事が返ってきたんです。
Rock oN:すごい展開ですね!高野:丁度、時代が円高だったというのもあるかもしれませんね。彼は日本びいきなんだけど、ビジネスチャンスだとも思ってたのかもしれません。僕以外に色んなアーティストが素材を送ったようですが、トッドが選んでくれたのは僕とレピッシュだったんです。丁度、XTCの「スカイラーキング」の成功でトッド・ラングレンのプロデュースが注目されてた時期でしたし。
 1989年。トッド・ラングレンのUTOPIA SOUND STUDIO。NEOTEKのコンソール(たしか32in?)OTARI 24トラックアナログMTR、EVENTIDE H-3000、YAMAHA REV-7など。音源はFAIRLIGHT Ⅲ、PROPHET-5、ROLAND U-110、DX-7。
1989年。トッド・ラングレンのUTOPIA SOUND STUDIO。NEOTEKのコンソール(たしか32in?)OTARI 24トラックアナログMTR、EVENTIDE H-3000、YAMAHA REV-7など。音源はFAIRLIGHT Ⅲ、PROPHET-5、ROLAND U-110、DX-7。
高野:僕のスケジュールが結構タイトで、その年の春にセカンドアルバム「RING」のレコーディングを終え、全国ツアーを2回演り、すぐ秋にはウッドストックにあるトッドのスタジオへ渡米し、レコーディングだったんです。曲を仕上げる時間がなく、書きかけのままトッドの元に行ったんです。最初の1週間は向こうで曲を仕上げる作業をして、僕としてはアレンジをトッドに手伝ってもらい、なんならオーバープロデュースさえもして欲しいという感じだったんですが、彼は手伝ってくれなかったですねぇ。
高野:先日、トッドと対談する機会があって、彼に言われたんですが、デモテープの段階で僕のやりたいことがはっきりしてたので、「プロデューサーとして自分がやることはあまり無かった」と言ってました。唯一アレンジが大きく変わったのは「べステンダンク」で、最初、アコギメインのバンドっぽいアレンジだったんですが、「これはイマイチだな」とトッドが言って、いきなりキーボードを弾き始め、メインになってる裏打ちのリフを入れてくれたんです。あと2〜3曲はコーラスのアイデアを出してくれたりしましたが、アレンジで手伝ってくれたのはそれくらいで、僕のレコーディングに関して、トッドはエンジニアに徹してた部分が大きかったです。もちろん、トッドは何もしてない訳じゃなくて、彼独特のミュージシャン的なデフォルメを施したサウンドメイキングは彼にしかできないもので、普通のエンジニアではありえないほどの極端なイコライジングやモジュレーションも、かけ録りだったりします。テイクの善し悪しの判断についても、「集中力なんてそんなに何時間も続かないから、徹夜作業なんて無意味だ」と言って、長くても7〜8時間くらい作業をやったら「今日は終わり」ということになってました。
Rock oN:トッドのスタジオはどんな様子でしたか?高野:OTARI のアナログ24 チャンネルとNEOTEK というメーカーの30chくらいのコンソールでした。トッドには3rd アルバム「CUE」に続き、4thアルバム「AWAKENING」の2枚をプロデュースしてもらったんですが、「AWAKENING」の時はコンソールのモニター回線がかなり接触不良を起こしてて、「下からつっかえ棒をすれば大丈夫だよ」みたいなことを言っていて、そんな状態でアルバムを作ってました(笑)。24 チャンネルあるうちのクリックトラックを最後に消して、1トラックだけで歌入れをしたこともあったんですが、そういう昔ながらのレコーディングスタイルを経験できたのはとても貴重でした。その頃のレコーディングは、今に比べると決してハイファイとは言えないですが、いいパフォーマンスの瞬間を沢山捉えてるし、現にそのアルバムが自分のキャリアにとって、一番ヒットした代表作になっていることを考えると、トッドの言う「サウンドは音楽のヒエラルキーの下の方にあって、一番大事なのは楽曲、そして演奏と歌だ」ということに自然と頷けるんです。もちろん過去にはたくさんトラックを使って緻密に編集してボーカルトラックを作ったこともありますけど、1トラックだけ使い、パンチインだけで直したテイクで「虹の都へ」が成り立ってることを考えると、編集で完璧なテイクをつくるんじゃなくて、いい瞬間を捉えることが録音の本質なんだと、身をもって体験しました。
Rock oN:普通の環境では経験できない、いい話ですね。高野:他に面白いエピソードとしては、当時、トッドはお気に入りのADAの1Uのギター用真空管プリアンプを使っていて、いきなりギターのシールドをそれに挿してライン録りしようとするんですよ。今みたいに、いいアンプシミュレーターがなかった時代だし、それまでギターは必ずアンプを鳴らして録ってたので、「ちょっと待って! ラインですか?? エレキギターはアンプで鳴らしたいんですが」と言ったら、トッドは「なんで?」って聞き返してきたんです(笑)。結局折衷案で、そのプリアンプを通した後にアンプにつないで鳴らしたんですが、どうしてもその真空管プリを使いたかったようです(笑)。それから「虹の都へ」のアコギも、トッドのオベーション12弦を借りたんですが、迷わずラインのみで録ってました(笑)
DAW時代。情報が溢れることの幸と不幸について
 Rock oN:今のコンピューターやDAW による制作環境について思うところはありますか?
Rock oN:今のコンピューターやDAW による制作環境について思うところはありますか?
高野:「夢のようだな」と思いますね( 笑)。いまだに。Logic Pro X のDrummer 機能なんて信じられないですよ( 笑)。あれはすごい!! でも、DAW は諸刃の剣のようなところがあって、ルールを決めないとだめだな、と思います。
Rock oN:どんなルールですか?高野:僕は必ず、歌と演奏は1曲通して録音するようにしてて、それが出来ない状態では録らないようにしてます。歌詞や構成などがちゃんと頭に入ってる状態で録りたいです。もちろんエディットも施しますが、よりよくなるためのエディットは意味があると思いますが、DAW を使ってブロックを組み立てるような曲作りはしないです。歌は3 テイクくらいに収めて、そのいいとこを繋ぐ感じですね。ギターはこれまでのサウンドプロデュースの経験が活きていて、割と自由に弾けるようになったのと、難しいことはやらないようにしてるので、あまり直すことがなくなりました。
Rock oN:トッドと同じく、作業が早いんですね?高野:いじり倒す事が好きじゃないです。それもトッドの影響ですね。彼がミックスにかける時間は平均1曲につき1時間程度でした。トッドはやっぱり天才的なところがあって、耳だけでどんどん判断していくんです。録ってる最中におおかた最終イメージを描いていて、その仕上げとしてミックス作業を行う、という感じです。もちろん、結果としてクリエイティブなものが出来れば、DAWでエディットを細かく施すようなスタイルであっても手法は問わないです。クリエイティブな意味あるエディットという面で、ジェームス・ブレークはすごいと思います。彼一人でDAWのメイキングをして、かつ自分のキーボード演奏と歌で楽曲の芯を強く定めてるのでライブも力強い。それに、サポートメンバー二人の力量もすごい!!
高野:僕がピンポン録音で作ってた時代に比べると、選択できる環境が夢のようにたくさんあって、僕自身もその多さに、逆に押しつぶされそうになりますよ(笑)。最近買ったソフトシンセのプリセットも全部聞いてないし、結局、選ぶサウンドはいくつかに決まってしまったり。そこは幸か不幸か、という感じもします。不便で「ああ、本当はこうしたいのに!」といった飢えみたいなのがあったほうが、実はクリエイティブに対する衝動が湧きやすかったんじゃないかな、と思う事もあります。「選択肢の多さでクリエイティビティを枯渇させてどうすんだ?」みたいなことも思いますよ。
若者と接する事で見返す自分自身の創造の源泉
Rock oN:京都精華大学で若い人に教えることを始められたそうですが、いかがですか?
高野:ポピュラーカルチャー学部 ポピュラーカルチャー学科 音楽コースで教えることを始め、日常的に若い世代に接するようになって、色々話をしたんですが、最初はすごくカルチャーショックでした。僕が若い頃の情報に飢えてた状況と真逆で、彼らは「情報に擦れてる」感じと言うか。僕が学生の頃は、もちろんインターネットや携帯電話もないので電話やメールも来ないし、テレビも夜中までやってなく、夜の早々に情報から遮断され、その分、夜が長かったし、そんな時は自分と向き合うしかなかったです。そんな不便な時代に曲作りを始めたというのは、実は、誇るべきオールドスクールなんじゃないかなとも思います。
Rock oN:大学ではどんなことを教えられてるんですか?高野:ソングライティング手法やアイデアの着想法を教えてますが、僕は一度もソングライティングを学んだ事がなく、全部自己流でここまで来たので、今、自己分析をしてるところでもあるんですよ。僕は「どういうきっかけで曲を書く事ができるようになり、インスピレーションはどこから湧いてきたのだろう?」と考えるいい機会になってるんです。
Rock oN:なるほど。人に教えるってどうですか?高野:学生それぞれにモチベーションが違うし、楽器をやらない子もいたりして大変ですね。「ばらばらの個性を持つ一人一人に対しても応用の効く発想法って何だろう?」と自問自答してます。機材のことでいうと、特にスピーカーなんですが、今の10代の子って音楽をスピーカーで聞くことが極端に少ないんですよ。家にもスピーカーが付いてる機材はラップトップのパソコンかテレビくらいしかない。
Rock oN:特に、低音を感じるためにスピーカーは重要ですよね?高野:そうなんです。僕もミックスしてて一番悩むのが低音の扱い方で、そこだけ不安が残るので、マスタリングだけはエンジニアさんに任せて、低音の問題を解決するようにしてます。
Rock oN:これからの若い世代にとって、音楽を仕事にして食べて行くって、より難しくなると思うのですが?高野:そうですね。1つのアドバイスとしてですが、自分がやってることがどのくらいのレベルなのか、自分の作る音楽がどれくらい人に受け入れられてるのか、ということを早い時期に知るべきだと思います。今ならYouTubeやニコニコ動画にアップして、どのくらいリアクションが返ってくるのかを確認するのもいいと思います。それともう1つ。なるべく誰かと一緒に作業して欲しいな、と思います。一人でやってる子があまりにも多いですよ。僕も宅録で、一人で音楽を作ることから始めましたが、時代が変わり、同じ時間を誰かと共有することが大事になってきてると思います。ライブでのオーディエンスとの関係もそうですしね。録音芸術というものの価値観が、今、崩壊しつつあるとも言えるし、これから違う意味を持ってくるような気もしています。
Rock oN:少し話を変えて、最近気に入ってる機材はありますか?高野:Universal Audio UAD-2のプラグインで、音響空間エミュレーションを行う「Ocean Way Studios」プラグインがいいですね。本当に優秀で、これを挿すと、自分がEMI時代に録っていた大きいスタジオの感覚を思い出します。アンビエンスって本当に重要だなと思いますね。マイクも今、探してて、これまでスタジオで録る時はエンジニアさんのチョイスに任せてたので、そんなにこだわりがなかったんですが、これから25周年を記念した作品を作るにあたって、自分との相性がいい1本を探そうかなと思ってます。EQをすることなく、自分の声に合うような製品に出会えればいいですね。
Rock oN:今後のご予定をお伺いできますか?高野:10 月でデビュー25 周年になり、以降の1 年間をアニバーサリーイヤーとして、まずアルバムを3 枚同時リリースし、全国ツアーをやります。そのツアーの中で新曲を演奏しながら仕上げつつ、来年の10 月までにオリジナルアルバムをもう1 枚リリースする予定です。ここで公約しますが、25 周年なので25曲入りにします!
Rock oN:配信等もあって「アルバム」の持つ価値や意味が変わりつつありますよね?高野:確かにそうですね。でも、せっかくやるならアルバムを作ることをこの機会に楽しみたいなと思っています。僕がデビューした年がアナログレコードからCDに本格的にスイッチした年で、それから25年経ち、CDというフォーマットがそろそろ揺らいでるので、ここであえて「CDでアルバムを作る」というのは意義深いことだと思ってるんです。もともとアルバムサイズってハードウェアの都合で作られたものだから、そう考えれば、時代と共に無くなってしまっても全然おかしなことではないし、「アルバム」というフォーマットがまだこれから先、必要とされるのか分らないですが、僕のキャリアの25年はCDの25年と重なるので、その締めくくりとして、いいCD、いいアルバムを作りたいなと思っています。
Rock oN:最後の質問ですが、高野さんにとって音楽とは何でしょうか?高野:自分の大半が音楽で出来てるし、人生の大事な物や価値観、アートに対する考え方なども音楽から吸収してきたし、なにより、出会ってきた人とのつながりも音楽からもらったものなので、水や空気と同じように当たり前の存在でありながら、生きるために必要不可欠なものですね。そして何年経っても奥が深くて、一生かけて探し求めるような手の届かないようなものでもあります。面白いですよね。

「宅録少年であり、YMO に影響を受け、ビートルズやトッドラングレンが好きで...などなど、高野さんに関するいくつかの情報の断片を、メディアを通し耳にしてましたが、今回、改めてお話を伺い、強く印象に残ったのが「ソングライターとしての価値基準」という言葉でした。 自分が「オリジナリティにこだわってしまう性分である」ということは、ポップミュージックを作るクリエーターにとってどういうことなのか? 話を世の中全てに当てはめ一般化してしまうと、答えが出ない問いかもしれませんが、「小さい頃から発明家を夢見てた少年が大人になり、その気持ちを持ち続けて音楽を作ってる」そういった高野さんの個人的な経緯を経て出て来た言葉だとすれば、「なるほど!」とスッと腑に落ち、飾ることない真摯な言葉として受け止めることができました。 デビュー25 年ということで、ますます、これからのご活躍も楽しみですが、高野さんのような今でも自分と向き合う、現役感に満ちた先生に音楽を習えるとあれば、学校の生徒が羨ましい限りです!
このコーナーでは、音を作り出す活動をされている方の出演を募集しています。ミュージシャン、サウンドエンジニア、作曲家、アレンジャー、はたまた音効さんや声優さんなどなど。音楽機材に興味を持っているかたなら、なおOKです。お気軽に、下アドレスまでご連絡下さい。また、ご感想、ご希望等もお待ちしております。連絡先アドレス : store-support@miroc.co.jp