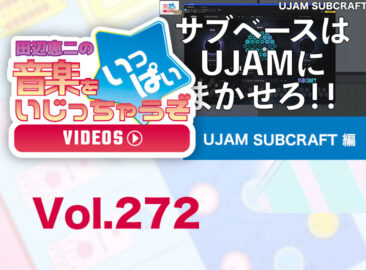あなたの楽曲制作にヒントをもたらす数々のノウハウ記事に加え、膨大な動画コンテンツは制作トレンド&Tipsの集大成!
KORGがARP Instruments社の共同創業者であるDavid Friend氏をアドバイザーに迎え復活を果たした ARP ODYSSEY!当時の回路を完全再現しただけでなく、3世代分のVCFや、VCAを歪ませるDRIVEスイッチを搭載。まさに当時のままの音でありながら過去最高の機能と完成度を誇るアナログシンセサイザーです。
この ARP ODYSSEYを株式会社マリモレコーズの代表取締役であり、作曲家、エンジニア、プロデューサー、DJなど幅広く活動する江夏 正晃 氏がレビュー。自らモジュラーシンセを駆使したシンセユニット『FILTER KYODAI』で表現活動をするなど、特にシンセサイザーに造詣が深い江夏 氏は蘇ったARP ODYSSEYをどう見たのか。ここからどうぞお楽しみください。
江夏 正晃 氏 meets ARP ODYSSEY
ARP ODYSSEYといえば現代のシンセサイザーの歴史を語るうえでMINIMOOGと同じくらい各所で影響を与えてきたシンセサイザー。私もオリジナルのODYSSEYはいろんな楽曲で使わせてもらっています。
リードサウンドでも、ベースサウンドも簡単に作れるわかりやすい構造はMINIMOOGより幅の広い音作りが出来、サンプルアンドホールドやピッチエンベロープを使ったSEなんかは映画でもたくさん使われていました。私もちょっとしたSEはODYSSEYで作ることも良くあります。
そんなオリジナルのODYSSEYはもちろん手に入れることはなかなか難しく、ビンテージ価格もどんどん上がり、簡単に手に入れることが出来なくなってきています。オリジナルに忠実に再現したという復刻版ODYSSEYはサイズも小さくなり、価格もかなり抑えられています。
[eStoreClipper2A mdin=’35686′ blocklocate=’CPB’ img=’LINK’] [/eStoreClipper2A]オリジナルとの違い
さて、実際の音ですが、オリジナル(Rev.2)と比べてみましたが、まったく同じとは言いませんが、ODYSSEYであることは間違いありません。アナログ機器ですし、経年変化を考えれば、当時新しいODYSSEYはこんな音がしていたんだろうと想像できます。そしてこの復刻盤ODYSSEYはオリジナルの各リビジョンで違ったフィルターをスイッチ一つで再現できます。
私も比べたことがなかったですのが、こんな違いがあったんですね。そして復刻版ODYSSEYにはMIDIもUSBもついています。CCには対応していませんが、NOTE情報は受けられますし、送れます。ということは現代のワークフローにもスムーズに取り込めます。プラグインソフトでもODYSSEYはたくさん出ていますが、せっかくのチャンス、ハードウェアとしてのODYSSEYを触ってみてはどうでしょう。
さて、復刻版ODYSSEYはただの復刻版ではありません。各所で工夫がされています。先述したリビジョンごとのフィルタータイプが選べることの他に個人的に気に入ったのがDRIVEスイッチです。このスイッチを入れると一発で存在感のある音に変身します。VCAをドライブさせることで新しいODYSSEYの一面が現れます。ベースサウンドなどに応用すると、オリジナルより強烈なうねる音作りが出来ます。
実は最近よく感じるのですが、プラグインばかり使っていたワークフローより、こういったアナログシンセなんかを使うと、音を重ねなくても存在感のある音作りが出来るように思うのです。
もちろんアナログの良さもあると思うのですが、ハードウェアを操作する感覚はプラグインを操作する感覚とは違ってくるので、音に対する向き合い方も変わってくるのではないかと感じています。ODYSSEYはちょっとしたエディットでサウンドは激変していきます。そんな面白さもこの復刻盤ODYSSEYにはしたためられています。
また細かい仕様なのですが、ポルタメント奏法をする際にトランスポーズを切り合える際にポルタメントがついてくる仕様とついてこない仕様とが小さいスイッチで切り替えられます。因みにRev.2はついてこない仕様になっていたので、新鮮に感じました。実に細かいところまで研究されつくして復刻されたODYSSEYは現代ならではODYSSEYを楽しめる仕様になっているのです。
こんな方にオススメ
鍵盤を使って、いままで幾多のアーティストが演奏してきたことを再現するもよし、DAWやステップシーケンサーにシーケンスを組んで、音色を変化させながら演奏するもよし、使い方は千差万別です。個人的にはODYSSEYならではのPPC(Proportional Pitch Control)を使って、独特のベンド奏法やモジュレーション奏法を試してみるのも楽しいでしょう。
ホイールとは違った感覚で演奏が出来ます。また、CV/GATEも搭載しています。最近盛り上がりをみせているモジュラーシンセと組み合わせて使うこともできます。使用方法は本当にさまざまです。是非皆さんの制作環境に合わせてこの復刻盤ODYSSEYを使ってみてはいかがでしょう。
まとめ
発表から少し遅れて発売になったものの、その分完成度はかなり高い製品になっていると思います。オリジナルより少し小さくなった復刻版ODYSSEYは場所も取らず、DAWの横やキーボードスタンドに乗せてもあまり圧迫感はありません。ビンテージを使うときの不安定さやメンテナンスも考えなくてもよいこともとてもありがたいことです。
ただ、一般的な現代のシンセサイザーと違ってまずはチューニングから始めなければなりません。(昔のアナログシンセはチューニングとの戦いだったんですね。)その昔YMOがチューナーを置いて、演奏していたのもうなずけます。
すなわちギターのように演奏前にはチューニングする必要があります。(SEなんかの場合は必要ないときもありますが。)MINIMOOGのように温度が一定になるまでピッチが暴れるようなことはありませんが、2つのオシレーターのピッチをそれなりに合わせなければなりません。レコーディングが終わってからピッチがおかしい!なんてこともあります。(私もよく遭遇するので、ビンテージやアナログシンセのピッチには気を遣います。)
ちょっと不便に感じるかもしれませんが、なんでもパソコンの中で完結させるのではなくこうやって、現代に復活したODYSSEYなんかを制作の中に入れてみるのも面白いかもしれません。私もODYSSEYをはじめ、たくさんのハードウェアシンセを楽曲制作の中に使うようにしています。数年前の制作環境とは一変しました!一期一会の面白さがこういった製品にはあるんです。
一度お店に足を運んで触ってみてはいかがでしょう?きっとその面白さ、不便さからくる楽しさがわかってもらえると思います。そして私から一点だけ忠告しておきましょう。ARP ODYSSEYはエディットが面白くて作業が進まないこともあるのでご注意を。
[eStoreClipper2A mdin=’35686′ blocklocate=’CPB’ img=’LINK’] [/eStoreClipper2A]
記事内に掲載されている価格は 2015年7月28日 時点での価格となります。
最新記事ピックアップ