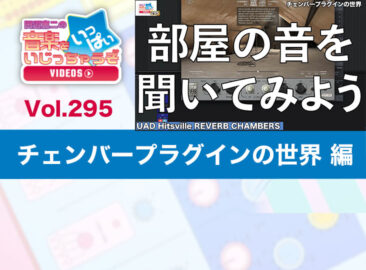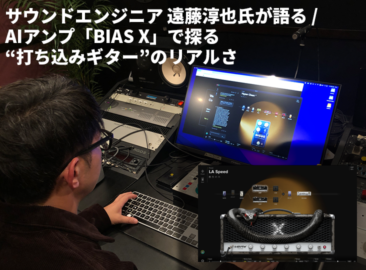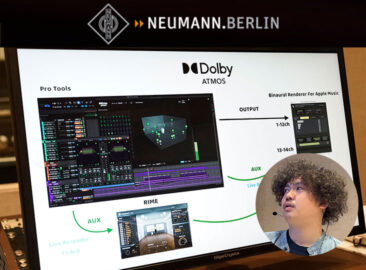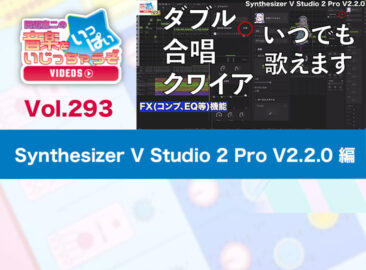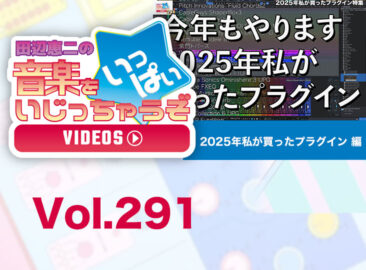あなたの楽曲制作にヒントをもたらす数々のノウハウ記事に加え、膨大な動画コンテンツは制作トレンド&Tipsの集大成!

小型アクティブスピーカーの私的優位性。制作用モニタースピーカーに求められるもの。
私は15年前の転居時にかなりの断捨離を敢行して楽器(シンセやサンプラー等)やエフェクター類のそのほとんど全てを処分して以来自宅制作環境で使うスピーカーは小ぶりなアクティブスピーカー一択となっている。
パッシブスピーカーに比したアクティブスピーカーの優位性を上げろと言われれば、比較的安上がり、省スペース、設置ポジションが比較的自由、等々あるだろうが私的一番の選択理由は、アンプが要らない、である。アンプ不要となると省スペースに加えて使うケーブルは減るし当然接点も減る。その結果制作時のモニターに違和感を覚えた際のチェックポイントが少なくて済むということになるわけで、これは根が面倒くさがりな自分には大きいのだ。おまけに下手をすると音への不要な色付けになりかねないアンプ選びに悩むことからも解放されるわけである。アンプ選びも醍醐味であるオーディオの楽しみ方とは全く逆方向を向いているのだが、そもそもリスニング用のシステムと制作用のシステムは違って当然なのだ。
例えばスピーカー。リスニング用のスピーカーはそこに至る前の機器の味付けを含めて”より自分好みの音が鳴るものが良いスピーカー”であってよいのだが、制作用のスピーカーは録音された、あるいはジェネレートされた音がなるべく無味無臭で”より正確な音が鳴るものが良いスピーカー”となる。分かり難い言い方になるが”より気持ちよくしてくれるのがリスニング用”、”なかなか気持ちよくしてくれないのが制作用”というような違い。要するに「ギターが細い」とか「リバーブのタイムが長すぎる」とか、粗は粗としてそのまま再現して欲しいのが制作用モニタースピーカーというものなのだ。


D3Vの印象とその特性。パッシブラジエーターと3 x 3 x 3 のフィルター補正。
そんな私の元にD3Vが届いたのはあるアーティストとのコラボレーション作品の制作中のタイミングであった。それまでかなり長く使っていたスピーカーにはヘタリも感じていたので制作途中にも関わらず以後の作業はD3Vで続ける方向で早速入れ替え。その第一印象だが、先ずは中域の解像度、奥行きを含めたステレオ定位の再現度の良さに好感触。へタリのせいもあったであろうが、それまで使っていたものよりも立体感が段違いに良い。
次に小型スピーカーを語るときに重要な点の一つである低域の再現度についてだが、本機はペアのそれぞれのボディ左右に直径5cmほどのパッシブラジエーターなる駆動ユニットが組み込まれておりそれが低域の伸びを担っているとのことだが、正直同クラスの小型アクティブスピーカー群の中では確実に抜きん出ていると思う。45Hzまで出るとなっているカタログスペックに嘘偽り無しである。
EDMに限らずベースがフィーチャーされる傾向にある昨今、加えて必ずと言っていいほどサブベースを鳴らすジャンルもあり、音作りにおいてキックとベースの音作り、関係の判断と調整が以前に増して大切かつ難しくなっているが、その点にフォーカスする作業において本機は頼れる低域の明瞭度を有している。
もう一つ、本機を語る上で欠かせないのが「DSPによる音響補正機能」であろう。背面に図1にある3つのスイッチがあり、その組み合わせによって部屋のモニタリング環境特性に合わせたサウンド調整が可能となっている。
3つのスイッチはそれぞれ3択で、
・スピーカーの配置:スタンド上、コーナーの無い壁際のデスク上、コーナー寄りのデスク上
・デスクのサイズ:スタンド上、大きめのデスク上、小さめのデスク上
・部屋の吸音処理:十分に吸音、そこそこ吸音、吸音無し
となっていて、そのスイッチの組み合わせの結果であるユーザー設定によって図2にあるような補正フィルタリングが行われる。
ここで私の目を引いたのはデスクの大小によるフィルタリングの違いである。大きめのデスクでは中低域の200Hzを-6db(Q=2)、中高域の1500Hzを-4db(Q=2,5)補正、小さめのデスクでは300Hzを-3db(Q=1)、2000Hzを-2db(Q=2)補正する。このグラフを見て「あぁ、そういえばD3VはDesktop Monitorだったな」とメーカー内でのはっきりした位置付けと開発陣の本気を再確認させられた。デスクトップ(机の天板)にスピーカーを置けば共振は必ず発生し、低域が膨らみ過ぎたり中域の分離が悪くなりと音像が不明瞭になってしまったりするもので、その悪化程度は天板の材質や面積によって違ってくるわけだが、本機は天板の面積(デスクの大きさ)による共振や反射を考慮した補正を施しているわけである。
この3種のスイッチによるユーザー設定によってフィルター補正の仕方が変わるのはとても親切であると共になかなかに前向きに攻めた仕様だ。この仕様は言うまでもないがAIの測定によって自動的に最適な再生環境を提供してくれるような代物ではないので、あくまで調整判断の指針として自分の耳でスイッチの組み合わせを色々吟味し自分の作業環境に一番しっくりきて仕上げの音像にゴールし易い設定をユーザー個々が見つけるという使い方がよいと思う。
実際私は当初のセッティング時にはデスクの大きさをSmallにしたのだが2曲ほどD3Vをメインモニターにして制作した過程において他の環境でチェックした結果も含めて今はLargeに変えている。そして長い付き合いになりそうなので耳の高さに合わせるための卓上マイクスタンド(一般的なマイクスタンドの口径ならどこのメーカーのものでもOK)を先程注文した。


レッスン室での試用、比較試聴。モニタースピーカー導入の勧め。
本機が届いてから自宅での制作用モニターとして一月弱使ってみて大いに満足しているが、このレビューを書くにあたり他の環境でも試してみようと思い、教鞭を取らせていただいている洗足学園音楽大学のレッスン室に持ち込んで使用してみた。
大学にある多数のDAW使用レッスン室にはGENEREC、FOCAL、YAMAHA、PMC等々(勿論ADAM AUDIOも)、営業スタジオでも見かけるモニターも含めて信頼度の高いメーカー製の多様なアクティブスピーカーがランダムに設置されていて、そのランダムさは個人的には自分の耳のリフレッシュにも役立ってくれている。
今回はそういった複数のルームとスピーカーで自分のモニターチェック用の音源やレッスン生徒の制作中音源を用いて比較試聴してみたが、制作時の再生ボリュームで聴く限りD3Vは他のモニター(どれも容積では4〜5倍)に全く引けを取らないどころか対象機種によっては低域、中域の明瞭度で優っていたケースもあり、トラックをソロにしてプラグインの効果を調整したりするレッスン過程でも勿論私にとっても生徒にとっても違和感なくスムーズに作業をすることができた。
2024年度から大学で主に作曲、制作を教えるようになって数多くの音楽家の卵達と触れ合う機会が増えたこの一年半の間ずっと気になっていることがある。それは、スピーカーでのモニタリングの重要性がかなり疎かにされている、という傾向である。
思い返せば私が所謂プロと呼ばれる世界に足を踏み入れた頃は商業ベースでの音楽制作を自宅で完結できるケースはほぼ無く、多かれ少なかれ営業スタジオでの作業があり、十分に調整されたスタジオでの有能なエンジニア連との仕事を通してモニター環境の重要性を目の当たりにし身に染みて覚えていったわけだが、自宅で完結するためのツールも数多く存在し、また完結可能なジャンルの商業音楽も多い今現在、私が学んだような経験を与える機会が乏しいままにスピーカーとヘッドフォンの使い分けが最も効率的かつ質の向上に繋がるということを十分に理解してもらうことはなかなかどうして難しい。
話は少々それたけれど本機ADAM Audio D3Vはペアで43,000円(税込/2025.09.26現在)とその性能からしてコスパ激高である。制作用モニターとして決して入門機に留まらないそのパフォーマンスは前述のとおりである。
おそらくこのwebでこのレヴューを読んでいる方のほとんどは音楽制作に関わる、あるいは志す方々だと思うが、もしもあなたが私の前段の記述に思い当たる節があるとしたら、数万円以上する高価なプラグインを新たに購入するよりも先に本機の導入を検討することをお勧めする。
録音からマスタリングまでの全てのステージにおいて、より良いモニタリング環境は最終的な音楽パッケージの質の向上に直結するとても大事な要素なのだから。
こちらもご覧ください
記事内に掲載されている価格は 2025年9月29日 時点での価格となります。
最新記事ピックアップ