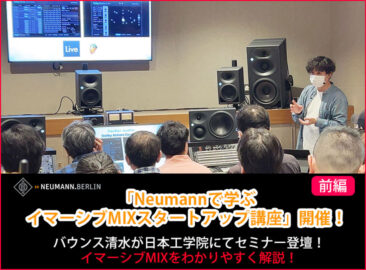あなたの楽曲制作にヒントをもたらす数々のノウハウ記事に加え、膨大な動画コンテンツは制作トレンド&Tipsの集大成!

みなさんこんにちは!普段ドラムの音源など、ドラム関連を中心にレビューしているPD安田が、今回新発売となったRUPERT NEVE DESIGNS「RNDI」を使用してベースをメインとしたデモ曲を作成してみました!
私は本職はドラムですが、高校時代に吹奏楽でコントラバスを担当しましたので、作曲やアレンジなどする際は自身でレコーディングもやっています。
普段はUniversal Audio LA-610 mk2を使用して、直接ベースを繋ぐことも多いのですが、今回このRNDIを使用してサウンドをぜひ皆さんに確認をして頂きたいと思います!
それでは早速ですが、ベースメインでレコーディングしたデモ曲を聴いてみましょう!
RNDIを使用してベースメインのオリジナルデモソング!
いかがだったでしょうか?構成は最初はピアノのバッキングをメインにベースラインを中心に演奏し、後半はドラムとベースのみでメロディもベースで構成しています。なおドラムの音源はFxpansion「BFD3」を使用しています!
 そして今回のシステム紹介ですが「RNDI」は電源の取り方がマイクプリからのファンタムによって電源を取る形になっています。そこでLA-610のマイクプリ部分のファンタムを利用し「Fodera Bass Imperial & Emperor ⅱ」→「RUPERT NEVE DESIGNS RNDI」→「Universal Audio LA-610 mk2」→「Apogee Symphony I/O」→「Avid Pro Tools」の流れでレコーディングを行いました。
そして今回のシステム紹介ですが「RNDI」は電源の取り方がマイクプリからのファンタムによって電源を取る形になっています。そこでLA-610のマイクプリ部分のファンタムを利用し「Fodera Bass Imperial & Emperor ⅱ」→「RUPERT NEVE DESIGNS RNDI」→「Universal Audio LA-610 mk2」→「Apogee Symphony I/O」→「Avid Pro Tools」の流れでレコーディングを行いました。
使用したベースのベースライン部分はFodera「Imperial」の5弦ベースで、メロディラインは「Emperor II」の6弦で弾いています。これらのベースはパッシブとアクティブの切り替えが出来ますが、今回はパッシブでレコーディングを行っています。
Foderaのサウンドは結構派手なサウンドが特徴的で、派手さがありつつもベースの図太いサウンドも兼ね備えています。これはデモを聴けばFoderaのサウンドがよくわかるかと思います。
ただ、持ち運びも考慮したためか本体が非常に軽いため、ライブなどの際、ベースアンプの上に置いてセッティングするケースも多いかと思いますが、何か固定をしておかないと、ケーブルの重みも考慮し、落下するケースと現場でのトラブルも考えられます。
もしハードなパフォーマンスを行う際は本体が固定できるよう固定できるようなケースなどを別途用意した方がいいかもしれません。
しかし弾いてて思う事は、RUPERT NEVE DESIGNSの「RNDI」はとにかくサウンドに癖がない!ということです。
ずばりベースそのままのサウンドキャプチャーする事ができ、非常にクリアに録れる素晴らしいDIとなっていますので、ぜひ多くの現場で活躍していただければと思います!
続いてPro Toolsのセッションでインサートしたプラグインは主にMcDSPでCompressorBankで少々頭を抑えつつ、FilterBankでHi-Passと200Hzあたりをややカット、そして5KHzあたりをややブーストしている状態となっており、±2dbの設定にしております。
途中のスラップ間奏部分はAmplitubeで激しくコンプを掛けていますが、メロディとベースラインは先ほどの紹介通り、Comp、EQの軽い補正で整えた形で仕上げています。
今回ベースそのもののサウンドが良いと言うこともありますが、何よりもRNDIがクリアすぎるので、ベースをしっかりキャプチャーしたい!という場所では持ってこいの逸品かと思います。正直スラップ演奏は得意ではありませんが、ライン録りでもこんな感じに仕上がるので、是非ベース録りには必ず使用したい機材ですね。
ライン録りと同時にアンプ接続も可能!
この写真を見ていただくと分かる通り、Input端子の隣に「THUR」端子が用意されています。THUR端子がある事で、レコーディングで直接送るのと同時に、アンプにも接続が可能なので、ラインとアンプ録りと同時に演奏する事が出来ます。
つまり、レコーディング現場ではなくライブ現場においても、PA側とアンプ側に送る事が出来るので、モニタリングも含めて出音のサウンドもクリアに且つ、最高のパフォーマンスをする事が出来ます。
 そして本体自体が非常にコンパクトで片手で簡単に掴んで持ち運びもできるので、リハーサルスタジオの移動からライブステージなどなど、気軽に全国ツアーで回ることも可能です!
そして本体自体が非常にコンパクトで片手で簡単に掴んで持ち運びもできるので、リハーサルスタジオの移動からライブステージなどなど、気軽に全国ツアーで回ることも可能です!
また非常にユニークな機能として、これまでの使用方法は表パネルにもある「インストゥルメントモード」にして接続をしていましたが、パワーアンプの出力からこのRNDIに接続する事も可能です。
つまる所、ベースのパワーアンプからこのRNDIに繋いで、アンプでの音作りを終えてからのライン送りとアンプ送りが可能となっています。
このような機能は今までにあまりなく大変珍しい機能となっていますので、ベーシストは是非このDIを使用して、アンプからアンプに送られるサウンドをキャプチャーしてください!そして、せっかくここまでクリアで忠実なサウンドが得られるので、是非ベース本体にも投資をして行ってください!
いかがだったでしょうか!レコーディングに使用してクリアなライン録りも良し、そしてアンプから出力される信号に対してのサウンドをキャプチャーするのも良し!レコーディングスタジオ、リハーサルスタジオ、そしてライブ現場など、どこに持っていっても大活躍は間違いないでしょう!
RNDIを使用しての細かい接続や、その他の使用方法などご質問がありましたら、お気軽にPD安田までご相談ください!
[eStoreClipper1A mdin=’35517′ img=’ZOOM’]“Neve”のキャラクターも持ちながらも、より現代の音楽制作のツールとしてニーヴ氏のこだわりのDI[/eStoreClipper1A]関連記事
Musikmesse 2015ショーレポート記事内に、あのRupert Neve Designへのインタビューを掲載。エンジニアでなくとも音楽制作をする者であれば誰しもが魅了されるあのNEVEサウンドを作ったRupert Neve氏に、プロダクト開発秘話やNEVEブランドからRupert Neve Designsに至る現在までそのヒストリーとポリシーをインタビュー!
[LinkButton shop=” type=’3′]http://www.miroc.co.jp/show-report/nab_musikmesse2015/archives/2294[/LinkButton]記事内に掲載されている価格は 2015年4月22日 時点での価格となります。
最新記事ピックアップ