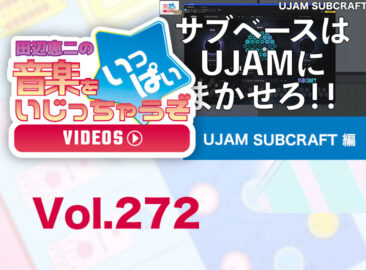国内外のあらゆるイベントをいち早くレポート! またブランドや製品誕生の秘話に迫るDEEPなインタビューを掲載!
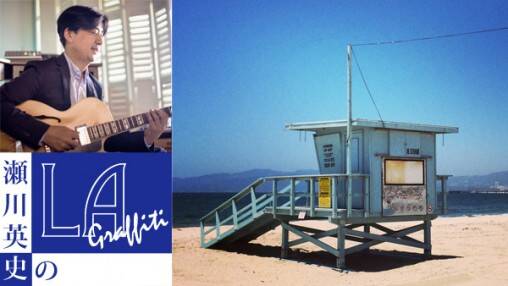
ロサンゼルスをベースにした生活へ。その理由は、、、
実はですね、今年の5月からロサンゼルスに住んでいます。先週も打ち合わせのために東京に戻りましたが、基本的にはロサンゼルスをベースにしています。ここ数年海外の短編映画や海外のCMの仕事のオーダーが来るようになったんですがその殆どがコンペなんです。そのコンペの勝率は日本国内のそれに比べて実はかなり低いんです。恥ずかしい話なんですけどね、、、理由は幾つかありますが、やはり現地のCMを見る機会が少ないし、過去に留学等の経験もないんでアメリカだったらアメリカの文化をやっぱりよく分かってないんですね。実際グローバル企業のCMの方がまだ勝率は高くて、ドメスティックな商品や会社になればなるほど勝率は悪い、、、とそんな感じだったんです。だからロンドンから依頼されたRolexのワールドワイドのCMで三回戦勝ち抜きでコンペに勝った次の週にニューヨークのプロダクションから依頼されたアメリカのドッグフードのCMでは一回戦敗退。ロンドンの代理店から依頼された、中国のある大都市のテレビ局のインターナショナル向けのチャンネルのための音楽を納品した後に参加した、メキシコのデオドラントのCMコンペも一回戦負け(涙)。
海外からの評価。「じゃあアメリカに住んでみようかな。」
それと今年の2月にカンヌで開催されたmidem(世界中の音楽出版社が集まる見本市、コンベンションね)に参加したんです。自分の作品集を携えて行ったところ思いの外評判良く、イギリスのライブラリーミュージック(このライブラリーの仕事は日本の業界ではあまり馴染みがないので追い追い説明する、かも?)の会社に楽曲提供のお誘いを受けたり、パリのCM音楽プロダクションに一緒に仕事をしようと言われたり。そんなこんなで、じゃあアメリカに住んでみようかなと。アメリカに行って毎日テレビを観てれば勝てるんじゃないか?そんな単純な発想で来てしまいました、アメリカ・ロサンゼルス(そこまでのプロセスはそんなに簡単じゃないんですけどまあそれは省略)。実際は紆余曲折あったんですが、こういう事は深く考えてもしょうがないでしょ?元々岩手の盛岡という田舎から東京でスタジオミュージシャンになりたくて上京した時だって、これと言って約束されたものは何もなかったわけだし、上京しない事には始まらない。ならば上京するかと。その時と同じ感じだよね。さて、今回の連載は、、、
さて、話変わって先の10月、LAで開催されたAESを覗きに行った時にロックオンカンパニー代表の前田さんとお会いしました。お茶しながらなんで僕が今LAに居るのかを話してる時に(前田さんもその場の思いつきだと思うんですが)、「そんな話しをうちのWEB用に書いて下さいよ!」と言われて「何書いてもいいですか?」「いいです!」「じゃあ書きます!」というやり取りをしたんですね。それで今この原稿を書いてるわけです。音楽や機材の話だけじゃないかもしれないし、観光ネタもありやなしやで考えてますけど、現地からの視点で何かを伝えられるようにはしますね。
 とりあえず初回なんで「LA」の話しから。日本ではロサンゼルスの事を「ロス」と呼びますが、現地で「Los」と言っても殆ど通じません。Losが付く地名はアメリカ国内に何箇所かあるから「どこのロスだよ」って感じなのかな。六本木の外国人に「ロス」と言って通じるのは彼らは日本人がLAの事を”ロス”と呼ぶと理解してるからだね。最近の日本のファッション誌は既に「流行のLAファッション、アボットキニー特集」的な感じでロスではなくてLAという呼び方に切り替えてるよね。テレビは相変わらず「ロス、ロス」と言ってるから日本国内ではしばらくこの呼称が続くんだろうね。ま、日本の中だけならなんて呼ぼうとそれほど問題ないかも知れないけど、日本から出た場合実際どうなのかというのは知っておいて損はないと思う。とにかくネイティブの人達はロサンゼルスの事をLA(エルエー)と呼んでます。それと同じような事がもう一つ。LAの国際空港をLAXと書きますが、これを「ラックス、ラックス」と呼んでるのも日本人だけです。実は僕も以前そうでした(汗)。ある時「あのさ〜、お前がさっきからラックス、ラックスって言ってるのはもしかしてLAX(エルエーエックス)の事か?」と指摘され気がついた次第です。確かにCDG、HND、FRAとどこも略さないで呼ぶもんね。
とりあえず初回なんで「LA」の話しから。日本ではロサンゼルスの事を「ロス」と呼びますが、現地で「Los」と言っても殆ど通じません。Losが付く地名はアメリカ国内に何箇所かあるから「どこのロスだよ」って感じなのかな。六本木の外国人に「ロス」と言って通じるのは彼らは日本人がLAの事を”ロス”と呼ぶと理解してるからだね。最近の日本のファッション誌は既に「流行のLAファッション、アボットキニー特集」的な感じでロスではなくてLAという呼び方に切り替えてるよね。テレビは相変わらず「ロス、ロス」と言ってるから日本国内ではしばらくこの呼称が続くんだろうね。ま、日本の中だけならなんて呼ぼうとそれほど問題ないかも知れないけど、日本から出た場合実際どうなのかというのは知っておいて損はないと思う。とにかくネイティブの人達はロサンゼルスの事をLA(エルエー)と呼んでます。それと同じような事がもう一つ。LAの国際空港をLAXと書きますが、これを「ラックス、ラックス」と呼んでるのも日本人だけです。実は僕も以前そうでした(汗)。ある時「あのさ〜、お前がさっきからラックス、ラックスって言ってるのはもしかしてLAX(エルエーエックス)の事か?」と指摘され気がついた次第です。確かにCDG、HND、FRAとどこも略さないで呼ぶもんね。
LAの機材サポート事情 〜 ケース1 : Grace Design社 〜

入出力の豊富さ、レンジの正確さ、音色のナチュラルさが抜群に良いので現在東京
でもLAでも使っている。機材にもスピーカーにもそれぞれキャラクターがあるので
モニターコントロールには透明感と操作性の簡潔さを求めている
m905の場合は症状を伝えたら、「君のm905を送ってもらって修理してもいいけど、その症状は右チャンネルのコンデンサーのハンダ付けが浮いてるんだ。だから指示するから自分でハンダし直しても治るよ。」とメールのリプライが来て、さすがにこれは本社に送って修理してもらいました。ギターのエフェクター(英語だとStomp Boxね)くらいだったら自分でハンダ付けするけど、モニターコントロールは要の機材だからやっぱり、ハンダ付けは自分じゃなくて、本社にやってもらいたいよね(笑)。この場合は代替え機(Loaner/ローンナーと呼びます)がFedexで送られてきて、その箱に自分のm905を入れて送り返し、修理後はその逆って流れ。
LAの機材サポート事情 〜 ケース2 : Universal Audio社、
英文メールのマナー〜
とまあこんな感じで今後しばらくLAから原稿書きますのでよろしく!
こちらもご覧下さい。
記事内に掲載されている価格は 2014年12月12日 時点での価格となります。
最新記事ピックアップ