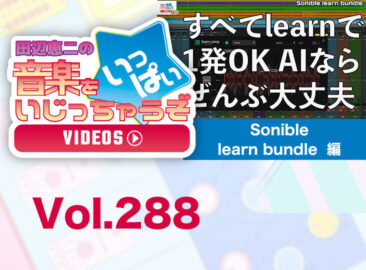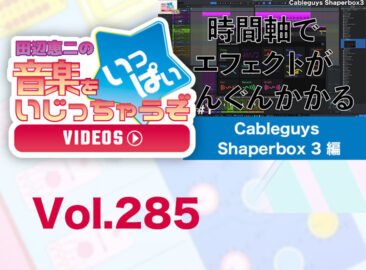国内外のあらゆるイベントをいち早くレポート! またブランドや製品誕生の秘話に迫るDEEPなインタビューを掲載!

キング オブ アナログシンセサイザーMoog Musicシンセサイザーの魅力に迫る特集『History of the Moog Music』の新コンテンツ!
Moog博士とMoog Musicの歴史はこちらの『History of the Moog Music』bob’s Timeline にまとめました。しかし当時の日本ではMoogシンセはどう受け入れられ、どう広がっていったのでしょうか。
その疑問をミュージシャンとして多岐に渡る活動で知られる辻 敦尊 氏に投げかけ、1980年代あたりのMoog上陸の時代や、音楽業界の動向などを伺いました。
Moogシンセとの出会い
Rock oN(以下R):まず、辻さんが初めてシンセサイザーに触れられた時のことを教えていただけますか。
辻 敦尊 氏(以下T):僕が始めた頃っていうのは、1982、3年くらいなんですけれど、そのときはもうデジタルシンセに移行しつつあったんですね。アナログもあったんですけどDCOのものだったりしたので。RolandのSuperJX(JX-10)とかその辺が現行製品だった頃ですね。そして僕が初めて手にしたシンセはやっぱりデジタルシンセでした。チューニングも合うし、和音も出るので。
R:チューニングが簡単に合うっていうのは当時、楽器として大きなアドバンテージだったんでしょうね。今となっては当たり前の事のように思われてしまっていますが。
T:ええ。当時はモノフォニックシンセというものがよく理解できていなかったんです。「どうしてこういうものに需要があるんだろう?」って思っていました。なので僕は最初にDX27をファーストシンセとして手に入れたんです。
T:当時はお正月とかに、キーボードランドとかキーボードマガジンに、有名なキーボーディストのセットアップが載ることがありまして。彼らのラックに何が入ってるとかいうのが全部掲載されていたんです。
今もお正月になると、サンレコとかにプライベートスタジオの特集などが掲載されるじゃないですか。ああいう感じのキーボディスト版がお正月になると載っていたんです。
R:お正月なんですね(笑)。
T:そうなんです、一月号だったかな?で、その中にデビッドフォスターがプロデュースしていた頃のシカゴのライヴセットアップが載っていて。アルバム名で言うとCHICAGO16、17、18あたりの頃ですね。

Mini Moog 1972
そのセットアップ内容を見ていたらロバート・ラム、ビル・チャンプリン、2名のキーボディスト以外にもジェームズ・パンコウなど3名くらいがちっちゃい鍵盤をセットアップしていたんです。それが『Mini Moog』だったんです。
R:おおっ、きた! Mini Moog!
T:その他のキーボディストのセットアップを見てもMini Moogは多くありましたね。でも、やたらと木目だし、木のガワだし、古そうだなと。(リック・ウェイクマンか誰かが使ってるときだったと思います)「こいつはなんなんだ?」と。それがMoogとの出会いでした。最初はやっぱりMini Moog、つまりMoogイコールMini Moogというところから入りました。そして当時僕の好きなキーボディストはベースとして使っている人が多かったと記憶しています。
R:やっぱりMini Moogといえばベースサウンドですよね。
T:特に70年代後半から80年代ってシンセサウンドばりばりの頃ですから、ベーシストがいてもシンベ(シンセベース)の曲っていうのは多かったので、そういう曲をライヴで演奏する際にもMini Moogはよく使われていましたね。
例えばシカゴ(バンド)はブラス・ロックですけど、全曲全編でホーンセクションが鳴っているわけじゃないので。
R:手弾きのシンベサウンドって80年代音楽の特徴ですよね。
T:そうやってMoogを知って、音に触れるようになりました。Moogは中古楽器店にも多く並んでいました。ある時、某メーカーのアナログシンセが目当てで楽器店に行ったんですが、偶然そこにあったMini Moogを弾いてみたら、もう別格の音でした。
R:別格ですか。
T:「なるほど!」って感じで、そこからMoogを別格視するようになりました(笑)
R:その「別格」っていうのは、どういうところにそう感じたのでしょうか。
T:今も思うんですけれど、音を出すとまったく違う次元の音がするんですよね。
例えばギターとかもそうですけど、メディアに録音した後の音って、今の技術を持ってしてもまだ全ての音情報は入りきってないと思っています。そんな時は「今もまだDAWやレコーダーってまだまだ発展途上なんだなぁ」とか感じるんですが、その収めきらないほどの音の魅力(情報)を持っている楽器の一つとして、MiniMoogはあると思うんです。
まだまだ媒体に収めきれないほどの魅力、謎を秘めている楽器。だからアコースティック楽器と同じくらいの魅力を持っていると言っても過言ではないと思います。
R:なるほど。Moogシンセが「太い」とか「艶やか」って言われるのは「音の情報量が多いから」と捉えることができるんですね。
T:良い意味で荒い感じの音なんですよね。そして聴いたときに毎回驚きがある。今のデジタルシンセでもいい物ってたくさんありますけど、Mini Moogと勝負となったら、勝てる気はしませんね(笑)。。
R:音の太さで Mini Moogの右に出る者は無いでしょうね。
T:そのぐらい、やっぱり存在感っていうのが大きい、太い音だと思いますね。
Moogシンセは「そのリスクを背負ってでも持つ」
R:辻さんが初めて手に入れたMoogっていうのはやっぱりMini Moogですか?
T:いや、僕は実機で、自分所有のMoogは持ったことがないんですよ。
R:ええ!意外です。これまであんなにMini Moogの音が良いって言っていたのに。
T:Moogは先輩から借りたり、もしくは現場にあるものを使っています。
R:でもやっぱりお仕事で使われてるのって…
T:仕事となると、例えばスタジオなんかだと、決まった時間でできるだけ効率良くいいものを作らなければいけない。そういう時には安定していてすぐに音色をリコールできるArturiaのソフトシンセなどを使う事が多いです。
T:スタジオやライブでアナログシンセを使うのはリスクがあるんですよ。だから余程のことがないと使いません。でも例えば、自分のスタジオでやったりするような時間が許される時にはソフトシンセやバーチャルアナログシンセであらかじめアレンジは組み立てておいて、最終で実機の音に差し替えをしていくような事もします。
R:なるほど。
T:Moogシンセは「そのリスクを背負ってでも持つ」という人だけが持っている気がします。。だからアレンジャーさんよりキーボーディストさんが持ってる事の方が多いんじゃないでしょうか。
タンス
R:松武秀樹さんはトレードマークのモジュラーシンセ Moog III-Cを今でもステージで使ってますね。
T:すごいですよね。ちなみにMoog III-Cを「タンス」と呼ぶきっかけを作ったのは松武さんと聞いていますよ。Moog III-Cの角に和箪笥の補強金具を付けた事がそのきっかけだったそうな。タンスを持ってワールドツアーに行ったなんてほんとスゴイ挑戦だと思います。
R:アナログシンセの不安定さっていうのはリスクだって伺いましたけど、それを持って海外にツアーっていうのはすごい状態ですね。
T:ですよね。あの頃はMIDIも無く、使える技術も全然違ったでしょうし。
R:ステージ上の電圧が変わればチューニングが狂ってしまうんですよね。
T:年に何回か、松武さんとご一緒させてもらうときにMoog III-Cが登場するんですけど、やっぱりちょっと早めに電源を入れられてますね。
でも、去年かな。なんかのイベントのときに、電源を早めに入れすぎて、「ピッチが逆に高くなりすぎてしまった」とか言われていたような(笑)。
R:暖めすぎてもダメなんですね。奥が深い。
現行の製品でもMoogはやっぱりMoog製だなっていう音を感じる

Minimoog Voyager Old School
R:2002年のMinimoog Voyager発売から、Moogが色々と新しい製品を出してきています。
T:今のMoogの会社の製品は、Moog博士の技術や魂が受け継がれてる感じがしますね。
R:それはどういうところで感じられますか?
T:アナログシンセってProphet-5とかARP2600とか色々ありますけど、それぞれの会社の音がちゃんとあります。で、現行の製品でもMoogはやっぱりMoog製だなっていう音を感じるんです。やっぱりいい意味でバリバリした、荒い、太い、何か分からない要素はちゃんと含んでるっていう気がします。
R:比較的新しいSub Phattyは今どきのグリッチーでギリギリガリガリした音も出るんですが、それでもMoogの音っていうのがちゃんと受け継がれてるということでね。
T:そうですね。
R:今後、こんな製品出たらいいのにな、みたいなそういうことってありますか。
T:Moogと言えばLadder Filterじゃないですか。Moogerfoogersは良いんですけれど、いかんせんでかい(笑)。あれがもうちょっとコンパクトになって持ち歩けると、もっと面白いことできるのになって思うことはあります。
R:プロの現場だと、あのフィルターってどういう使い方をされるんですか。
T:僕なんかは、ギターとかで、何て言うんでしょう、飛び道具……。わかりやすい音じゃないんですよね。
でもその飛び道具系で使う感じですかね。だから「ピューン!」とかそういうような音じゃないけれど、不思議な、「モワワワワワワ」みたいな音を作ったりするようなときには、あの辺はやっぱり便利ですね。
R:なるほど、そうですか。Ladder Filterっていうと、ちょうどAPI500モジュールの「The Ladder API 500」がありますけど、もしかしたらそういう声が他にもあったんでしょうね。
じゃあ、シンセサイザーだったら、何かこんなのあったらいいのにな、みたいなのありますか?
T:モノシンセの音の太さでポリシンセが出てほしい。ポリシンセも分厚さはあるんですけど、でも各社、モノのものがやっぱり一番太い気はするんですよね。
だからあの太さで、ポリシンセっていうのが出たらそれはまた更に魅力だなあとは思います。3ポリくらいでも出てくれたら、本当にいいのになぁと思いますけど(笑)。
時代ごとのアナログシンセの見直され方の違い
R:辻さんは、80年代のシンセ全盛の時代から音楽をされてきて、デジタルシンセとアナログシンセが交互に評価される波を経験してきたと思うんですけど、最近またアナログが盛り返してきてきることをどう思われますか?
T:僕個人的な考えですが、80年代後半から90年代のアナログが見直されてきたことと、今のアナログが見直されてることって、多分、需要が違うと思っています。
R:その話、すごく興味があります。
T:ひとつは、僕らが使い始めた80年代の頃って、デジタルシンセで一番だったのはDX7だったわけですが、でもDX7のディスプレイってとっても小さい。あれで音作りはちょっとキツいよ、みたいなところがあって、多分アナログシンセの直感的な操作性っていうのが見直されていたんだと思っているんですね。
それに音を並べて聞いたとき。デジタルシンセをバーンって鳴らしても、比べるとやっぱりアナログのほうが全然太いっていう感じがあった。つまり当時は「直感的な操作性」と「音の太さ」で再評価された。
R:では今、アナログシンセが求められる理由は?
T:ソフトシンセ(おおきなディスプレイを含めて)とコントロールサーフェス製品によって操作性の課題はずいぶんと解決されてきました。なので今の一番の需要は所有欲にあると思っています。つまりアナログシンセ時代の人が大人になって「学生時代に憧れていたアナログシンセを!」とか「当時使っていたあのアナログシンセをもう一度!」のようなところに一番需要があると思うんです。もちろん音の太さなどの魅力を感じて求めている人も少なくないと思いますよ。
R:なるほど。すごく辻さんらしい視点だと思います。
自分で作った音への愛着
 R:ベテランの辻さんから、今からシンセを始めたいとか、若い人たちへ一言をいただけますか。
R:ベテランの辻さんから、今からシンセを始めたいとか、若い人たちへ一言をいただけますか。
T:音色を自分で作る事にぜひチャレンジしていってみてください!自分で作った音は愛着も湧くものですし、フレーズの評価を受けた時などは大きな自信にもつながっていくと思います。そもそも僕がマニュピレーターに憧れたのはそういう面に魅力を感じたからでもあるんです。例えば、昔のわかりやすいところでいうと、A-haっていましたよね。
R:はい。「テイク・オン・ミー」ですね。
T:タラララッチャッチャ……っていうあのフレーズとあの音は、一瞬聴いただけでもうあの曲だとわかりますし、あの音を作った人にとっては今も誇れるものになってると思うんですよね。
自分で作った音で構築された作品にはそれまで以上に、聴いてもらいたい要素が増えるものですから、ぜひオリジナル音色作りにも挑戦していってください!
R:そうですね。これからちゃんと音作ります(笑)。
最後に
プロミュージシャンの辻 敦尊 氏らしい視点と経験から見たMoogシンセ。プロが求める音、操作性、機能、そしてそれらの味わいを醸し出すMoogシンセの魅力の数々をお楽しみいただけたでしょうか。
辻 氏も言う「別格」で「メディアに収まりきらないほどの情報量をもった音」を手に入れるメリットは数え上げたらきりがないかもしれません。
シンセサイザーの中の一つではなくもう一段格上の、ピアノやギター、バイオリンに並ぶ楽器の一つとして、Moogシンセのサウンドをあなたのスタジオに導入してみてはいかがでしょうか。ぜひ御検討ください。
関連記事
記事内に掲載されている価格は 2014年3月11日 時点での価格となります。
最新記事ピックアップ