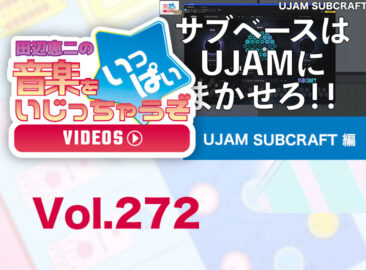あなたの楽曲制作にヒントをもたらす数々のノウハウ記事に加え、膨大な動画コンテンツは制作トレンド&Tipsの集大成!

作曲などモニタリングする上でヘッドフォンを選ぶコツですが、箇条書きで表すと
・着け心地がいいか?(自分の頭に良い感じか)
・サウンドは好みか?
・目的は何か?(録音か、Mixか?)
この3点を念頭に置き、実際に店頭で試聴いただくと選びやすいかと思います。(もちろんブランドの好みとか、見た目のこだわりとか、ご自身に説得できるものがあればそれで良いと思います!)

クリエイターの中でも人気のあるbeyerdynamicのDT7xxシリーズですが、DT700PRO Xのドライバーを引き継ぎつつ、全体はDT770 PROの側となっております。従って、この2モデルの間?と思いがちではありますが、実際に聞いてみて、3機種ともに特徴が違うので、本レビューではDT700PRO X、DT770PRO X、DT770 PROの3機種で比較をしていきたいと思います。それではレッツゴ
DT 770 PRO X Limited Edition(100周年モデル)

まず新しいモデルDT770PRO Xですが、後述のDT700の新しいドライバーユニットに加えて、筐体はDT770 PROとの組み合わせになっております。
これはすごく簡単に説明すると「軽くなって、新しいドライバーでモニタリング」となっております。音質はDT700PROよりもHighがややありまして、これはおそらく本体が軽くなった影響と、新品だった影響も大きいのですが、5kHz以上がしっかり出てきております。
それでいて低域、中域も確認ができ、全体を通してモニタリングが可能です。
DT700PRO X

当店の展示機でチェックを行いましたが、ある程度鳴らしている期間もありましたので、HighはDT770PROXよりも落ち着いて聴けて、筐体はやや重く、本体の内部的な密度もあるせいか、ここが影響しているようにも感じます。
それでも大きく被る形で使用できるので、メガネをかけている方でも痛くなく長時間の使用は可能なのではないかなと思います。
なお高域は落ち着いていると言いつつも、他のサウンドはそのままにどこか突出してる部分はなく、聴きやすい感じになっております。
DT770 PRO (80 Ohm)

最後にDT770 PROですが、軽さはDT770PRO Xと同じく、サウンドは今回の3機種の間という感じでした。
Xシリーズからはドライバーが強化されており、従来モデルも落ち着きはありつつも、満遍なくモニタリングできる機種かなと思います。
なお高域は他社の製品と比べてしっかり「キリ」っと出ているのがbeyerdynamicの特徴かなと思いますが、こういう高域はヘッドフォンが最も確認しやすく、最終的にiPhoneのイヤホンなどに落とし込んだ際に、通常の高域部分と中域、加えて低域のバランスを見る際に参考にしやすいのかなと思っております。(iPhoneのイヤホンだと高域のキリっとしている部分は聞こえず、低域に寄りがちなので慣れは必要ですが、参考になるかなと思います)
記事内に掲載されている価格は 2024年4月5日 時点での価格となります。
最新記事ピックアップ