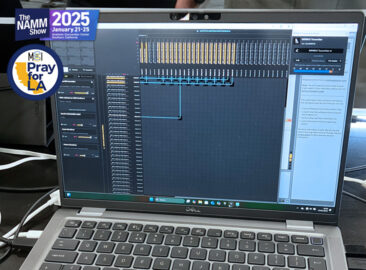国内外のあらゆるイベントをいち早くレポート! またブランドや製品誕生の秘話に迫るDEEPなインタビューを掲載!

単なるハードウェア音源モジュールの枠を超え、コンピュータベースの音楽制作環境との統合を目指したデスクトップ音源モジュール『Roland SonicCell』。その実力や如何に?
7月末に発売予定の『Roland SonicCell』!直前緊急レポートをマエストロ佐々木がお伝えします。(ご協力:ローランド様ありがとうございます。)今までにないコンピュータ環境前提のコンセプトとデスクトップ型のデザインが注目の的です。気になっているユーザーの方も多いのではないでしょうか。今までの音源は、ラックタイプ?という概念を打ち破り登場。

ではでは、触って触って・・・
まずは純粋な音源モジュールとして単独使用。電源を入れるとディスプレイが今までにない感じです。有機ELディスプレイを採用しているということで、視認性も良くGOOD。
Fantom-Xクラスの音源エンジン搭載という肝心のサウンドを聴いてみると、聞き慣れたローランドサウンドなのですが、今っぽいサウンドというのでしょうか、より明るくクリアでエッジが効いているように感じました。音色は約1000音色と膨大ですが、カテゴリーサーチで素早く探せます。また『SRXシリーズ』の音色拡張ボードを2枚増設可能なので、強化したい音色を追加可能です。FANTOM/XVシリーズにSRXボードを増設して使用しているユーザーの方の乗換えにも最適!
操作性に関しては、マニュアル無しで触ってみましたが、ユーザーインターフェースが非常によく考えられており、少ないボタンとカーソル1個のみでストレスなくエディットすることができました。

ここからが本番です。『SonicCell』をコンピュータ環境で使用。Mac G5 + Logic Pro 7.2の環境で試してみます。まずはDriver & Ediorソフトウェアをインストール。”簡易インストール”で何も問題なくOK。アンインストーラーも入っていて親切です。
インストール後、Logic Proのオーディオドラーバー設定を開くと、「おーっ!」SonicCellが選択可能です。(認識して当たり前なのですが、発売前のドライバーなので認識するか心配していました。)Logicのデモ曲を再生すると『SonicCell』のアウトプットから音が出ます。ノイズもなく安定性も問題ないのではないでしょうか。
次にインストゥルメント・トラックにSonicCell Editorをインサートしてみます。立ち上がる時にUSB経由で本体にライブラリを 読み込みにいくため若干時間がかかるようです。プラグインウィンドウが開き、早速エディターから音色を変更&エディット。ソフトシンセを使用している方なら違和感なく使用できそうです。エディットすると、これも当然ですが本体がリアルタイムで連動、この時点で本体を触る必要は全く無くなるので、ハードウェア音源を使用しているというよりは、ソフト音源を使用している感じです。
次にSonicCell EditorとSpectrasonics Stylus RMXを同時に立ち上げて簡単な打ち込みをしてみました。当然ですが両方の音がSonicCellからミックスされて出力。

簡単なチェックでしたが、チェックを終えての感想は、発売前の段階で、何の問題もなくコンピュータ環境で使用できたのは評価できるのではないでしょうか。コンピュータ + SonicCellという極めてシンプルな組み合わせで、オーディオI/F、確実に128ボイスを鳴らせるオールインワン音源を含んだシステムが組めるのは未来的な感じがします。しかも非常にハイコストパフォーマンス!!
ちなみに、ある筋から「こんな形にしおって ライブで使う時どこに置くんじゃー!」というクレーム(?)がはいり、スタンドに設置可能なアダプターも発売されるそうです。
そんなわけで、なかなかやるな〜〜の新コンセプト音源の登場です。「SonicCell」なる命名は、なかなか的を得ていると思えます!固定音源の安定感と拡張性をダイレクトPCに取り込むもよし、ライブで持って回るもよし。現在Rock oNでは、ばしばしご予約受付中です。ご不明点は、担当マエストロ佐々木まで TEL03-3477-1756!!
記事内に掲載されている価格は 2007年7月12日 時点での価格となります。
最新記事ピックアップ