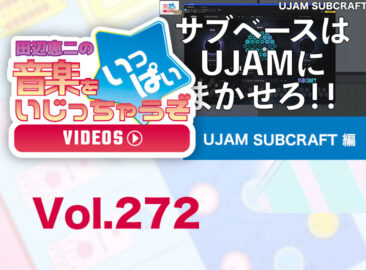あなたの楽曲制作にヒントをもたらす数々のノウハウ記事に加え、膨大な動画コンテンツは制作トレンド&Tipsの集大成!
話題のNeumann MT 48がついに10月26日発売しました!今年のNAMMでの発表以降、今月ようやく製品仕様や価格なども明らかになりましたが、待望の実機もRock oN渋谷店に到着!
ということで今回はRock oNスタッフ・バウンス清水が、Neumann MT48を実機を使ってみて、その音質や使い勝手を徹底レビュー!
このチェックにはRock oNのウェビナーなどでお馴染み、Neumann日本代理店であるゼンハイザー・ジャパン真野氏のご協力のもと、製品開発の背景や詳細なスペックなども併せてご紹介します。
Neumann初のオーディオインターフェイス 開発の背景
バウンス清水 : ついにNeumann初のオーディオインターフェイスMT 48が発売しました!これはめでたい!
Sennheiser 真野氏(以下、真野氏) : ありがとうございます!
Rock oN : まずはNeumann初のオーディオインターフェイスということで、MT 48を開発した背景からお伺いしたいと思います。
Sennheiser 真野氏 : 今年になってNeumannはMerging Technologiesを買収しまして、その技術やノウハウを踏襲したことを受けて、今回MT 48を開発した形になっています。
これまでNeumannはマイクロフォンをメインとして長年製品を開発・販売してきましたが、最近ではスピーカーやヘッドホンの製品も積極的にリリースしてきました。それらはベストインプット・ベストアウトプットということですが、音の入り口と出口の部分だけでしたが、それらを繋ぐ真ん中の部分を宝石に見立てて「ミッシング・ジュエル」と呼んで、Neumannのサウンドをきちんと届けられるインターフェイスを作りたいと考えてMT 48をリリースしました。
Rock oN : なるほど。Neumannブランドのマイクロフォンやスピーカーを十分活かせるインターフェイスということですね。
バウンス清水 : 自分の第一印象としては…小さくていいなと思いました(笑)。専用ケースに入れて外に持ち運びがしやすいコンパクトさがありがたいと。それとMacだとドライバーがいらないというのもいいですね!これが制作現場でクリエイターが入れ替わり立ち替わり来るような場所に一台置いてあるインターフェイスとしても重宝すると思いますよ。来てケーブルを挿してすぐに音を出す、という感じで使えますから。
Rock oN : 製品としてMT 48はどういったユーザーをターゲットとして想定されているのでしょうか?
真野氏 : ターゲットとしているユーザーとしては「本格的なホームレコーディングをされる方」「音楽制作をやっているコンポーザー・クリエイター」のほかにも、「配信などでリアルタイムの処理を必要とされている方」「放送、映画の編集室」などを想定しています。
Rock oN : それではMT 48のセールスポイントは何でしょうか?
真野氏 : まず第一に音質の部分です。価格帯としては30万円ということで比較的オーディオインターフェイスではハイエンドな部類になるかと思いますが、ADをする段階でのダイナミックレンジが同クラス製品より4倍高い分解能力を持っており、います。136dBAまで分解できます。
簡単にいうとTLM 103自体のダイナミックレンジが131dBまでなんですが、それを余裕で越えられるレンジをMT 48は持っているので、TLM 103で収録した音を余すところまで再現することができます。ゲインを最大78dBまで上げることができるので、非常にゲインの小さいリボンマイクなども含めて、様々なマイクロフォンに対応できる仕様になっています。ヘッドホンの出力部分に関してもインピーダンスが35mΩという非常に小さいことによって、高いインピーダンスのヘッドホンも十分に再生できる音質を持っています。
ほかにもMT 48はインターフェイスとしての機能は大半網羅しているので、その辺もご紹介できたらと思っています。
MT 48でボーカルレコーディングを想定したセッティング
バウンス清水:今回は実機をお借りして一番セッティングとしてあり得そうな、MT48を使ったボーカルレコーディングを想定して組んでみました。
MT 48はとても自由度が高くて、小さいミキサーを用意すればキューボックスとしてトークバックを載せたりとかもできます。まず1&2Chにオケの2mix、3chに自分のボーカルの返し、4chにクリックが流れるみたいな形で、仮想キューボックスみたいな感じでセッティングしています。
バウンス清水:ボーカルの録り音にコンプやEQ、マイクプリアンプもかけられるのも便利ですね。
真野氏 : 最終的にDAWに出力する際に、録音したドライの音とエフェクトをかけた音、両方出すこともできるしどちらか任意の音だけを出すこともできます。
バウンス清水:リバーブも入ってるんですよね。
真野氏 : そうです。レコーディング時にボーカルの方に返すリバーブのセンド量やルームの広さなども自由に変えられます。
真野氏 : インプットがアナログで4ch、コンボジャックが2つ、フロントにはPhone端子で入るマイク/ライン入力が2ch、4系統のアナログ出力(XLRで2ch、Phone Outで2ch)があって、さらに2系統で超低インピーダンスのヘッドホンアウトがあります。ほかにはADATを接続することで、さらに8ch増設することも可能です。
バウンス清水:ミキサー4系統備えているというのはなかなかないですね。ここが柔軟に組めるのが便利でいいです。あとはトークバックのマイクが内蔵されているところも大きなところですね。トークバックボタンを押して接続したミキサーに声を送るセッティングもができるのもとても便利です。
画期的な「ヘッドホン・クロスフィード」機能
バウンス清水 : 他にいいなと思った機能が、「ヘッドホン・クロスフィード」という機能があって、これはヘッドホンのLRバランスを調整できるんですよ。これでスピーカーのセットアップに近い音像でヘッドホンのモニタリングができるようになるんです。
真野氏:通常のヘッドホンだとLRが完全に分離した状態なので0%なんですが、 MT 48は0〜100%の間でヘッドホンの音像を調整できて、100%だとモノラルになるという機能なんです。これがあるとヘッドホンで作業するのが苦手だという方でも便利だと思います。
バウンス清水 : 他に同じ機能がある製品としてはRMEのADIシリーズくらいしかないと思うので、これは貴重ですね。
Merging TechnologiesのANUBISとの違い
Rock oN : 先ほどMerging Technologiesを買収して、その技術やノウハウを踏襲したとおっしゃっていました。Merging Technologiesが出しているAD/DAインターフェースANUBISとMT 48の外観が似ていますが、違いというのはどこでしょう?
バウンス清水:たしかにANUBISに似てますよね。
真野氏 : ANUBISはAES67接続を軸に作られているのに対して、MT 48はAES67だけでなくUSBやADATにも接続できるというのが大きな違いですね。それにANUBISはサラウンドのモニターコントローラーの機能が実装されていたりもしますし、色々なことができるが故に接続するのがちょっと複雑だったりするんです。それをMT 48はもっと音楽制作の現場でシンプルに使いやすいように、NeumannがANUBISをベースにテイラーメイドした製品と言えます。
バウンス清水:ANUBISはネットワークコントローラーっていう位置付けもあるんですけど、オーディオインターフェイスの機能にフォーカスして作られたのがMT 48って感じですかね。
Rock oN : MT 48の音質の印象はどうでしょう?
バウンス清水:音の解像度が高くて、一世代先の音がしているなって印象でした。Prism SoundのLyraとかRMEのADIといった競合となりそうなオーディオインターフェイスと比較してみたんですけど、解像度は高かった印象ですね。
Merging Technologies HP
https://www.merging.com/products/interfaces/merging+anubis
本体のタッチスクリーンだけではない操作画面!
真野氏 : 他にも本体のタッチスクリーン以外で操作できる方法が2パターンあります。ひとつはIPアドレスを打てばブラウザ上で全体が見られるもの、もう一つは本体と同じ画面でリモート操作するPCアプリがあります。
バウンス清水:iPadでも同じネットワークに行けばブラウザ上で操作できるし、画面も見られるのでブース内にiPadを用意してミックスを自分用のバランスに調節することもできるんで便利ですよね。
★ただいまRock oN渋谷店に、MT 48展示中!

話題のオーディオインターフェースNEUMANN MT 48が展示中!操作感や音質など気になっている方は多いのではないでしょうか。
当店ではすぐにお聴きいただけるようセットアップしてあります👍お気軽にご来店ください!
関連記事

Neumann初のオーディオインターフェイスMT 48が10/26発売!
デジタルワークフローにNeumannクォリティをもたらす、プレミアムオーディオインターフェイス
記事内に掲載されている価格は 2023年10月27日 時点での価格となります。
最新記事ピックアップ