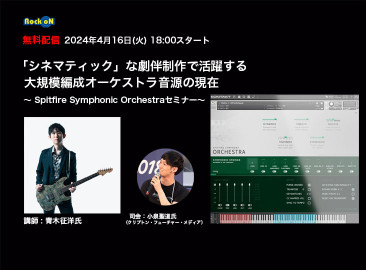“日本プロ音楽録音賞”は、優れた録音作品を手掛けたエンジニアを顕彰することで、エンジニアの技術向上と次世代エンジニアの発掘を図るために設立された顕彰制度。第1回は1994年に開催され、今年で第31回を迎えます。そこで今回は、第30回日本プロ音楽録音賞において若手エンジニアを顕彰するニュー・プロミネント賞を受賞されたお二人、ミキサーズラボの田宮空氏(写真左)と日本コロムビアの久志本恵里氏(写真右)をお迎えし、プロ録の印象や受賞作品に対するこだわりを中心に、日本プロ音楽録音賞運営委員長 高田英男氏の司会によりお話を伺いました。
第30回日本プロ音楽録音賞 ニュー・プロミネント賞2作品
Best Master Sound部門(ポップス、歌謡曲)エントリー作品
「堕楽」より「GAMESET」 Cena
ミキシング・エンジニア:田宮 空(株式会社ミキサーズラボ)
Best Master Sound部門(クラシック、ジャズ、フュージョン)エントリー作品
「わたしを束ねないで」より
「ロジャー・クィルター「3つのシェイクスピアの歌」Op.6より第2曲:愛しい人よ」
上村誠一(カウンターテナー)
ミキシング・エンジニア:久志本 恵里(日本コロムビア株式会社)
インタビュー本編
司会 : 高田 : 本日はお忙しい中お時間をいただきありがとうございます。日本プロ音楽録音賞(以降“プロ録”)は今年第31回の開催を決定し、9月1日より作品募集を開始しましたが、このプロ録というものを多くの方に知っていただくため、昨年度に若手エンジニアを対象としたニュー・プロミネント賞を受賞されたお二人に、お話を伺いたいと思います。
レコーディングエンジニアを目指すきっかけは?
それでは最初の質問ですが、それぞれ専門学校に入る時にはレコーディングエンジニアという職業を知っていたかとは思うのですが、レコーディングエンジニアを目指すきっかけについてお伺いいたします。まず田宮さんはいかがですか?

第31回日本プロ音楽録音賞 運営委員長 高田英男氏
田宮 : きっかけは、両親の影響と高校の担任の一言でした。父親が吉田拓郎さんの大ファンで家にアコースティックギターがあり、父は家族の誕生日にオリジナル曲を作ったりして家の中にはいつも音楽がありました。そんな父と一緒に歌うのが好きで、11歳くらいから父にギターの弾き方を教えてって音楽の世界に没頭していきました。ある時、自分のオリジナル曲をCD にしたいなと思い、父の知り合いが持っていたRolandのMTRとSM58を1本お借りして歌とギターを別々で録音(ダビング)してオリジナル音源をレコーディングし始めました。MTR内でComp・EQ・リバーブなどを触っているうちに「どうして市販のCDのような綺麗な音にならないんだろう」という疑問が湧いてきて、それをきっかけに“レコーディングエンジニア”という職業があることを知りました。MTRを弄り倒しているうちに、演奏や作曲よりも音創りに興味が向いていきました。14歳くらいの時には漠然とエンジニアになりたいと思っていた記憶があります。とはいえ高校進学後、家庭の事情もあって卒業後の進路希望では進学というのは頭には無くて、就職を希望していました。しかし担任が熱血教師で「お前のやりたいことはなんだ?自分の人生なんだからやりたいことがあるなら挑戦するべきだよ。」と強く背中を押され、“レコーディングエンジニア”になるために専門学校への進学を決意しました。
司会 : 高田 : そうでしたか。では、久志本さんはいかがでしたか?
久志本 : 音楽に触れた話からすると、子供の頃習い事でヴァイオリンを始めたのですが、一人で単音を鳴らしているのが寂しくて、そこまで好きではありませんでした。成長するにつれて私が好きになったのは、音楽というよりもドラマや映画のような映像作品で、その中で流れている劇伴がすごく好きになりました。劇伴はオーケストラだけではなく、打ち込みやバンドなど、いろんな編成がありますが、それらがドラマの世界観や登場人物の気持ちなどの、セリフや演技では表現し切れないものを作り出 していることにずっと憧れがありました。
当時はレコーディングの世界を全く知らず、「映像作品を作る側になりたい」と思っていました。なので高校からそのまま音響の専門学校に入ったわけではなく、実は空間演出的なものを学ぼうと大学に通い、さらに社会人を経験していたので専門学校に入学したのは24歳の時でした。
どこで音楽への転機が訪れたかと言うと、大学時代に学生オーケストラにヴァイオリンで入団し、自分が演奏側としてバランスを皆で考えたり、音づくりや表現をすることの面白さにはまっていったことがきっかけでした。自分が本当にやりたい表現は空間演出よりもむしろ音楽にあるのではないかと思い、専門学校に入ることを決意しました。
しかしこの時点でもどちらかと言うとMAをやろうかなと思っていましたが、その専門学校で現在の上司である塩澤さん(日本コロムビア)に出会いました。コンサートホー ルでのオーケストラ収録に連れて行ってもらったのですが、生のオーケストラ に感動したのはもちろん、収録した後塩澤さんが創られてきた作品にも凄く感動し、こんな職業があるのだと初めて認識しました。凄く大変な仕事ではありますが、現場の空気 や雰囲気含め、ここで働くことは自分に合っているのではないかと思い進む道を決断しました。
受賞作品における録音アプローチのポイントは?
司会 : 高田 : そう言った流れで塩澤さんに付いて行き、勉強することになったということですね。久志本さんに続けてお伺いします。今回受賞されたカウンターテナーの録音は、高崎芸術劇場の音楽ホールで録音されたということですが、マルチで録られたのですか?
久志本 : マルチですね、Pro Toolsで録りました。Mac、I/O一式を持って行って、フォーマットは96kHz/32bit-floatです。
司会 : 高田 :この作品はピアノとボーカルですが、マイクは何本ぐらい立てるのですか?
久志本 : メインマイクのステレオを近めのと遠めのものを無指向で2種類、そして舞台ヅラの方にピアノも歌も全体的に捉えるような間隔の広いステレオを単一指向性で1セット配置しました。オンマイクとしてボーカルのマイクはSCHOEPSを限りなく幅を狭めたステレオで、ピアノにはDPA4011をステレオバーを使って立てました。
司会 : 高田 :僕もホール録音を1回だけやったことがあるのですが、痛い目に合ってもうそれっきりで…(笑)、僕の先輩から「自分が録りたいメイン楽器にマイクを離して立てて、写真と同じでフォーカスが合った時には凄くダイナミックレンジも広く取れるし良いよ」と言う話を聞いたので、それをスタジオでやろうと思って試したのですが、スタジオはあんまり響かないので難しいのですが、でも今回の受賞作品を聞いた時に、本当にそのメインのカウンターテナーの声にフォーカスがピタッと合っていて、それにピアノがちょっと後ろにホワっとしていて、それがとっても立体感を感じて「これは凄いな」と思いました、正直。 今回久志本さんが、この作品作りにおいて何を意図していて、この作品でこんな所を聞いて欲しいみたいなことがあれば伺いたいのですが。

日本コロムビア 久志本恵里氏
久志本 : ありがとうございます。実はボーカルの上村さんに会うのもその日が初めてだったのです。カウンターテナーという世界も恥ずかしながら最初は知らなかったのですが、他のアーティストさんの作品も聴いたりして勉強し、男性が女性の音域を歌うという表現があることを学びました。プロデューサーさんにもお話を伺いましたが、男性の方が本来だと出せない音域を歌うということは、何かやっぱりすごく神秘的なイメージとかそういうところにつながる表現なのかなという印象を持ちました。後に、資料としていただいた映像とリハーサルの音源からご本人が大切にされている世界観を感じ取りイメージした上で現場に臨みました。
また、高崎芸術劇場の音楽ホールは響きが凄くクリアで綺麗です。実際に上村さんの歌声をホールの中で聴いた時の響きというのが非常に美しく澄んでとても綺麗だったので、その響きの感じは持ち帰りたい、でもそれが記録録音的にはならないようにしようと言うのが、自分の意図というよりは目標でした。音の記録ではなく、これをちゃんと音楽の世界観を表現するものとして持って帰れるように頑張ろうっていうことが収録時の一番の目標でした。
司会 : 高田 : 深いですね。なるほど、そうでしたか。やはりそう言う思いやそういうイメージがあって、あの音となるのですね。ありがとうございます。
次は田宮さんに伺います。僕らの頃には、作曲家とかアレンジャーが自分の家で作ったデモテープを聞いて、それをミュージシャンが集まって演奏して、生楽器で録音することでレコーディングが成立していましたが、田宮さんが受賞された今回の作品は、作曲の先生がアレンジして作ったトラッキングを、それを本番も使っているのですよね。
田宮 : はい、そうですね。
司会 : 高田 : それを使って新たに自分なりの音創りをして行くと言うことですね。そこが、今現役でバリバリやっているレコーディングエンジニアにとっての大きなポイントのような気がします。僕らの時代ってミュージシャンがスタジオに来て、デモテープを参考にしてレコーディングが進められて行くケースが多く、自分の音も作りやすかったのですが、打ち込み系でなおかつトラックが決まっていて、それを使って音楽を組み立てるという、今ならではのエンジニアの難しさがあると感じています。審査の会場で聴いた後にヘッドホンでも聞いたのですが、細かいところまで手を掛けているのが良く分かりました。そして、ボーカルのCenaさんのキャラクターもすごい世界を持っていますよね。こういった作品に対して、エンジニアとして何にこだわって、どういう思いでまとめて行ったのですか?

ミキサーズラボ 田宮空氏
田宮 : そうですね、僕も色々な現場に関わらせていただいていて、先ほどの話にあったような全部生楽器でスタジオ録音して作っていくスタイルの現場大好きです。それとは逆に打ち込み主体のトラッキングで、唯一の生楽器であるギターも宅録で弾いていたりという作品も多々あって、どちらにも違った良さがありますよね。今回の作品は後者で、ほぼ完成されたデモ音源があった上でミックスするわけですが、普段から心がけていることはデモ音源からいかに作者の意図を汲めるかというところです。デモの時点で表現できていること、表現し切れてない部分、それをミックス前にどれだけの解像度でイメージできるかはとても重要です。やりたいことを汲み取って噛み砕いた上で、何をすればもっと良くなるのかをよく考えます。今回でいうと、低域、中低域の整理がこの楽曲のミックスにおける肝だと思っていて、楽曲のジャンル的にも僕の大好きなビリーアイリッシュとかに近いものがあって、しっかりとサウンドのイメージを持ってつくり込んでいきました。又、この楽曲はボーカルRecもやらせていただいたのですが、いわゆるJ-POPのようなボーカルではなく、歌をどういう風に楽器として鳴らせるかっていうところを意識しながらボーカルを作り込んで行きました。セクションによってダブルにして広げたりとか、様々なサチュレーションを付加して声色を変化させたり。センターに 1 人の歌い手がいるっていうだけじゃなく、楽器としてこの楽曲を歌で表現するっていうところが凄くこだわったポイントです。 声ってやはり独特ですよね、どの楽器よりも音色が変化するし、言葉ごとに帯域も変わって、歌詞や感情もあるので、その一文字一文字で変わっていく音色に対して、文字ごとにEQ処理を変えたりしています。子音の処理とかもリズムを立てるようにオートメーションで細かく書いたり、トラックの一部として魅力的にハメて行くということを追求しました。Cenaさんの豊かな倍音を最大限に引き出すべく、EQやコンプだけでは出てこない成分は歪ませることで引き出したり、逆に出過ぎた帯域をEQ で削りその後に違う歪みを足してという作業繰り返し、何層にも重ねて歪を足していくみたいな音色作りになっています。ボーカルはドライな音色を基本にしているのですが、この楽曲は“二面性”を歌った楽曲なので要所で短めのディレイ+フォルマント処理みたいなエフェクトを使って人格の乖離みたいな表現にもチャレンジしています。
司会 : 高田 : 今の時代ならではですよね、デジタルならではの。
田宮 :はい、打ち込みは結構そういう言う風になって行くことが多いですね。
司会 : 高田 : それから、全体的に意識したことは「ストリーミング映え」って伺ったのですが、ダイナミックレンジを凄く取りたいので、マスタリングでレベルを最小限でお願いしたと言うことも衝撃でした。
田宮 : 今回は僕の中でもチャレンジで、普段はアーティストの方やクライアントさんから結構レベルを突っ込んでと言われることが多くて、「他の楽曲と並べた時に小さくならないように」って当たり前にみんなが意識することですよね。確かにその気持ちも凄く分かると思いつつも、Apple MusicだったりSpotifyだったり、最近のストリーミングは音量の自動調整機能とかもあったりしてアプリケーション上で結局変えられてしまうことも多いです。滅茶苦茶レベルを突っ込んだけど、結果的になんか並べたら小さくされちゃったりとか、最終的にどうなるか分からない中で、この楽曲の魅力をどう伝えようか考えた時に、Cenaさんの表現力だったり、楽曲の中でのダイナミクスが凄くあるのを魅力的に感じていたので、静かなセクションがあったりサビで急にドーンと音圧が上がったり、そういう表現をしたかったのでなるべくダイナミクスを生かして最小限のレベルの突っ込みでマスタリングエンジニアさんにお願いしました。レベルを突っ込まない代わりにミックスではラウドネスを意識して叩かれづらい音像にも注力しました。結果はリリースしてみないと分からないので思い切ったチャレンジでしたが、並んだ時に多少小さくなってしまったとしても、この楽曲をフルで聴いた後の満足感というところに振り切りたい旨をアーティストサイドにご相談したところ、是非やってみようということになりました。ミックスチェックでは想定くらいのマキシマイズ具合を仮に作ってアーティストサイドにミックス確認をしていただきました。そして想定レベル音源をマスタリングエンジニアさんにも参考にしてもらい「これ位のダイナミクスで考えていて、ダイナミックレンジが潰れるのであればこれ以上は行きたくない」と言う相談をしつつ進めたと言う感じです。結果、狙い通り小さくなることは無く楽曲の魅力をそのまま活かすことができたと思っています。
司会 : 高田 : 久志本さんにも、今回の作品のこだわりやこの部分を聞いて欲しいとかをもう少し伺いたいのですが、マスタリングはされたんですか?
久志本 : 先程の田宮さんのお話の様に細かくお願いするという感じでは全然なかったのですけれど、今まで私の携わった作品をほぼ全てマスタリングしてくださった信頼して尊敬している山下由美子さん(日本コロムビア)にお願いいたしました。「今回こんな感じで出来ました」と作品を持ち込んで「コンプレッサー入れたい?」と聞かれたので「そんなに入れたくないです」とか、そんなことをお話した上で何パターンか作っていただき方向性を決めました。それと今回は、日本語、ドイツ語、英語とか、色んな言語の曲があったので「言語ごとに雰囲気変えても良いかもしれない」とプロデューサーからご提案があったので、マスタリングの際に調整していただきました。
司会 : 高田 : 今回CDでしたっけ? メディアとしては。
久志本 : CDとハイレゾ配信です。
司会 : 高田 : コロムビアと言うのは、塩澤さん含めてアコースティックものに対する取り組みと言うのが、何か文化じゃないけどそう言うものが凄く強い感じなのでしょうか?
久志本 : そうですね、その塩澤さんのさらに上の代々の先輩方の時代から、みなさんホールものとかクラシックものに対する引き出しをたくさん持っていらっしゃって、私はまだまだ勉強している最中という感じです。
司会 : 高田 : 凄いですね! ちょっと話は変わりますけど、去年から30歳代までのエンジニアが応募した作品に対しては、審査時の評価採点をチャートにしてフィードバックしたのですが、あのチャートは参考になったのか、またはもっと別なフィードバックがあった方が良いのか、その辺りについて何かご意見はありますか?
田宮 : 嬉しかったです、細かく評価が示されていて。
久志本 : 私も嬉しかったです。私は自薦と制作ディレクターからの推薦と2作品のエントリーがあったのですが、受賞作品とは別の作品にもフィードバックをいただけたので、凄く自分の中では参考になりました。
田宮 : 自分の作品に対する評価バランスはこれ位なんだっていうのは分かりましたが、出来れば他の作品との比較はしたいなとは思いました。もちろん、自分の評価が分かるだけでも有難かったのですが、他の作品はどんな感じなんだろうみたいなのも知りたいかなと。
久志本 : 平均が点線で示されていたので、平均に対して自分の作品はここなんだと言うのは分かりました。
司会 : 高田 : あくまで平均ですから、その辺りの見せ方については課題がありますが、あれはあれで一つの参考として見ていただけたと言うことで良いですかね。ただ、全体の中で自分がどんな位置なのかが、もう少し分かり易くなるように検討してみます。
田宮 : ういうのが見られたら、もっと面白いかもしれないですね。
司会 : 高田 : ありがとうございます。それから、昨年のプロ録受賞作品が色々ありますが、なかなか聴く機会とかはないですよね。授賞式会場では作品紹介で再生されたものを聴かれたとは思いますが、何かお互いの作品を聴くとか、自身がやられているジャンルは聴いてみようみたいな感じはあるのですか。
田宮 : そうですね、他の受賞作品を授賞式会場で聴いて、それがきっかけ好きになった曲もあったり、自分が普段携わってないクラシックも音良いなと思ったり、これどうやって録音しているんだろうみたいな興味が湧いたりもしました。他に参加されていたエンジニアさんなどからも後日感想をいただいたり、とてもいい機会になりました。
久志本 : 私はCenaさんが個人的に凄く好きで、かっこいいと思って聞きました。
田宮 : ありがとうございます。
久志本 : さっきビリーアイリッシュの話が出たのですが、私も聴いた時にビリーアイリッシュみたいでかっこいいと思いました。
田宮 : ありがとうございます。表現出来ていたら嬉しいです。
久志本 : 表現、凄く感じました。誰っぽいとか言うとそれは逆に失礼なんじゃないかなと思って、口には出すべきではないと思いましたが、本当にそのお話が出て思わず名前を出してしまいました。とても細かく分析されていたり、緻密に積み重ねた作業を経ての表現と伺って、尊敬します。
田宮 : ありがとうございます。いやいやそんなことないです。
Music Awards Japanと連携した日本プロ音楽録音賞について
司会 : 高田 : 少し話題が変わりますが、昨年度から音楽主要5団体CEIPAが主催する「Music Awards Japan」と連携して、プロ録として何か一つの顕彰部門を作りたいと言うことで、今年は昨年の第30回プロ録の最優秀作品を「グランプリエンジニア賞」のノミネート対象として、その中から1作品を顕彰しました。内沼映二さんが担当されたビッグバンドの作品が今回は選ばれたのですが、その受賞コメント中に「是非こう言った賞を若いエンジニアに繋いで行って欲しい」と言う内容がありました。プロ録としても30回、そして新たにMusic Awards Japanとの連携をしたり、色んな事が変わって来ているので、もっとオープンで透明性があって若い人がどんどんエントリ―して来るようなプロ録運営の取り組みが出来たらいいなと思っています。それで今回のポスターもキャッチコピーを「NEXT STAGE~新しい未来へ踏み出そう」とし、若い人に向けてプロ録も変わって行きますので一緒に進んで行きませんかと言う思いを込めているのですが、プロ録に対してどんなイメージを持たれていますか。
田宮 : プロ録に応募させていただいたのは 2、3 回目位ですけど、内沼さん三浦さんや安達さん、尊敬する大先輩の方々が受賞されているのをアシスタント時代から見てきて、自分もいつかはっていうのは思っていました。もちろんいつも全力で全作品に向き合っていますが、これをプロ録に出してみたい思える挑戦的な作品にたくさん出会えるエンジニアになりたいと思えるので、とてもいい刺激になっていると思います。世の中には毎年素晴らしいミックスがたくさん出ていますが、それが応募されてないケースも沢山あるので、今後もっとプロ録が広まってさらに広いフィールドでたくさんの作品の中がお互いに良い影響を与え合えるような場になることを願っています。比較的若手の中で今回受賞させていただいて、同世代や若い方にも良い影響を与えられていたら嬉しいです。
司会 : 高田 : 久志本さんはいかがですか?
久志本 : そうですね、私まだ手掛けている作品がそんなに多くはないのですけど、一応自分関わった作品がある年は応募するようにしています。他の応募されて来る作品の中では全然まだまだかも知れないですが、携わったアーティストさんのために一生懸命頑張ったしそれを形として応募するというのは自分の中で節目になるかなって思っています。後輩のマスタリングエンジニアにももっと応募すれば良いのにと思って話をするのですが、レコーディングエンジニアの意向があるからと、自分の一存で出すのがちょっと難しく感じるのかもしれません。でも、私はそんなに人に相談しないで応募してしまいました。

若いエンジニアに向けたメッセージ
司会 : 高田 : 最後の質問になりますが、先程も言ったようにプロ録は若いエンジニアの方にどんどん参加して欲しいと思っています。全体のイメージとしては大学・専門学校を対象とした日本オーディオ協会主催の「ReC♪ST」という学生のための録音賞があって、プロになったら次の目標としてプロ録があるという形で繋がっていく流れとなって、若いエンジニアがプロで活躍するためのステータスを上げるチャンスになれば良いなと思っているんです。何かそう言う事も含めて、是非若い時にもっと挑戦してみようみたいな、若いエンジニアに向けて何かメッセージがあれば、一言いただけますでしょうか。
田宮 : そうですね、先程ちらっと言ったのですが、プロ録に自分が応募するにあたって、実はちょっとハードルを感じていました。内沼さん、三浦さん、安達さん、といった大尊敬する先輩方が受賞しているような場所で、そんな先輩方と肩を並べて作品を出すという事に最初はハードルを感じていました。でもいざ応募してみたら、これをきっかけに様々な受賞作品を知ることができたり、その音がどれもジャンルは違えども素晴らしいものばかりで、それを聴くことで自分の成⻑にも凄く繋がるなって思いました。普段自分だけでストリーミングを漁っていても出会えない作品に出会えますし、自分の好みで掘っている部分とは違う角度で音楽を深掘ることで視野も広がって刺激をもらえて、挑戦してみたい音像にも出会えると思ったので、僕みたいにハードルを感じずにバンバン若いエンジニアさんにも応募してほしいですね。結果はさておき、他の作品と聴き比べたりして、足りていない部分とか、こんなのもありなんだなとか、色々気付く良い機会にもなるので先ずは応募して欲しいです!
久志本 : そうですね、確かにそうだと思います。でも、そもそも自分がエンジニアとして仕事をすること自体に私は同じようなハードルを感じています。作品づくりに携わる以上、皆さんと同じ土俵に上がらなければならない、その覚悟の示しとしても結果はどうであれ、やはり自分の中の意識としてはそこに立ち向かっていかなければという気持ちがあります。これまで携わった各作品、そこに肩を並べられるように頑張ろうっていうのは凄く目標にしてきたことで、だからプロ録を意識してつくるっていうのはちょっと違うのですが、まず堂々と応募出来るようなクオリティでつくろうというひとつの目標に出来ると思います。そういう意味で、自分の意識を高めるものとしてプロ録に応募するという目標があるのは良いと思います。そうすると、皆何か良い作品をもっとつくろうとか、これまで受賞した作品のどんなところが良いのかを他人ごとではなく自分のこととして考えることが出来るし、それをきっかけに他の作品を知れるというのも田宮さんの仰る通りで、私もそう思います。また、こうして田宮さんのお話聞けたのも今日本当に刺激になりましたし、本当にすごく勉強になりました。こんな機会を得ることが実現して、すごく私は嬉しかったので、ありがとうございました。
司会 : 高田 : なかなか他社のエンジニアとの交流はないですよね。ましてやジャンルも違うしね。
田宮 : エンジニア同士って意外と会わないですよね。やっぱり1スタジオに1人ですから。
久志本 : 私の場合、身近に田宮さんの世代のエンジニアが少ないので凄く刺激になりました。お話できて嬉しかったです。
司会 : 高田 : 本当に今日はありがとうございました。
第31回日本プロ音楽録音賞
1. 実施目的
本賞は音楽文化と産業の発展の一翼を担う録音エンジニアが制作し応募した音楽録音作品について、エンジニアが有する音楽に対する感性、技術力等を評価することにより、各授賞区分の対象となる優秀作品および最優秀作品、並びに応募作品の中からベストパフォーマー賞を選定し、これに携わり制作を担ったエンジニアおよびベストパフォーマーのアーティストを顕彰することでエンジニアの技術向上と次世代エンジニアの発掘を図ることを目的とし、表彰を行うもの。
なお、優秀賞に選定された作品を音楽業界主要5団体が設立したCEIPAが開催する「Music Awards Japan 2026」の「グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ」ノミネート対象作品として、顕彰区分を超えた審査・評価により1作品を選定し顕彰する(予定)。
(PMRAJ:Professional Music Recording Award of Japan/日本プロ音楽録音賞の英語表記)
2. 審査対象
国内において企画され、2024年9月1日から2025年8月31日までの間に初めて国内で発売(2025年9月30日までにサンプル盤が配布されているものを含む)、または公に放送・配信された(2025年9月30日までの放送・配信が決定しているものを含む)音楽録音作品を審査の対象とする。
尚、旧譜の音源が新たにミキシングもしくはカッティングされた作品は応募が可能。但し、全ての作業を国外で行った作品を除く。
3. 応募資格者
(1)自薦:応募作品の制作に主要な役割を担ったエンジニア(Best Master Sound部門、アナログディスク部門はマスタリング・エンジニアを含む)とする。
(2)推薦:レコード会社・音楽出版社・番組制作会社等のディレクター、プロダクションの担当者、ミュージシャン等を含めた制作関係者、および運営委員会が推薦を依頼した関連各社とする。
4. 受賞資格者
最優秀作品および優秀作品の制作に主要な役割を担ったエンジニアとし、Best Master Sound部門、アナログディスク部門は1作品当り3名以内、Immersive部門については1作品当り2名以内とする。
5. 応募作品の分類および授賞区分
応募作品部門の分類および授賞区分は次の通り。
■Best Master Sound部門
クラシック、ジャズ、フュージョン(2ch)(CD、SACD、DVD、BD & 配信)
ポップス、歌謡曲(2ch)(CD、SACD、DVD、BD & 配信)
■Immersive部門
サラウンド作品全般、ジャンルを問わず
■アナログディスク部門
2chステレオ、33 1/3・45回転、ジャンルを問わず
■放送部門
2chステレオ/ラジオ番組:AM、FM、衛星放送、有線放送|テレビ番組:地上波、衛星放送
マルチchサラウンド/テレビ番組:地上波、衛星放送
■ベストパフォーマー賞
Best Master Sound部門、Immersive部門、アナログディスク部門の全応募作品よりベストパフォーマーを選定。
■ニュープロミネント賞
次世代を担うエンジニアの顕彰を目的として、30歳代までのエンジニアが担当した応募作品(Best Master Sound部門、Immersive部門、アナログディスク部門)よりニュープロミネント賞を選定。
6. 応募作品のメディア
■Best Master Sound部門
Best Master Sound部門のパッケージ作品は市販商品での応募とし、他の音声記録メディアによるコピーでの応募は受け付けません。ノンパッケージ作品のオーディオ・ファイル・フォーマットは、実際に配信されている音源と同等なファイルおよびフォーマットでの応募を基本とする(WAV、FLACおよびDSDIFF、DSF等)。
■Immersive部門
Immersive部門のパッケージ作品は市販商品での応募とし、ノンパッケージ作品はマルチチャンネル音源でのミックスマスターとして、ファイル・フォーマットはWAV、およびADM BWF、DSDIFF、DSF等とする。360 Reality Audio音源につきましては、360 WalkMix CreatorなどでExportされたMaster ADM、もしくは非プリレンダリング(Unprocessed)Exportなど360 WalkMix Playerで再生できるフォーマットでご応募を基本とし、48kHz 24bit LPCM(MPEG-H圧縮後にWAVに変換された24オブジェクト音源)のご応募でも可能とします。その他のデータについては事務局へご相談ください(※ご応募いただいた音源につきましては審査のみの再生となりますが、納品マスターを応募作品とする場合は必ず制作ご担当者の許諾を得て下さい)。
■放送部門
放送部門の2chステレオは、 ビデオ(XDCAM、P2)およびWAVファイル、マルチchサラウンドは、ビデオ(XDCAM、P2)でご応募下さい。(映像圧縮フォーマットについては、応募用紙の記載をご確認下さい)。
4K放送作品につきましては、審査の都合上2Kにダウンコンバートしてご応募下さい。尚、最大ch数は5.1chとし、22.2chで放送されている作品は、ダウンミックスされた作品での応募とします。
7. 応募作品数
応募作品の制作に主要な役割を担ったエンジニア1名1作品の応募を原則とします。但し、Immersive部門、アナログディスク部門、および応募作品を共同制作したエンジニア等及び推薦作品についてはこの限りではありません。
8. 応募方法
応募要項巻末の応募項目を確認いただき、一般社団法人日本音楽スタジオ協会ホームページ“第31回日本プロ音楽録音賞”ご案内ページ内リンク先にある各部門のエントリーフォームから必要項目をご入力いただくか、各部門の応募用紙をダウンロードいただき必要項目をご入力のうえ、運営事務局(japrs@japrs.or.jp)までメール添付にてお送りください。
パッケージ作品につきましては市販商品をお送りいただき、その他音源ファイル等につきましては、各種メディアにコピーもしくはアップロード等にてお送りください。
※応募作品の返却を希望される方は、送料をご負担いただくこととご了承下さい。
9. 応募受付期間
2025年9月1日(月)から9月30日(火)までの必着
10. 応募作品送付先
一般社団法人 日本音楽スタジオ協会
事務局長 内藤 重利
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町565-10 ビルデンスナイキ302
※事務局移転につき住所が変更となっておりますのでご注意ください。
E-mail:japrs@japrs.or.jp
TEL :03-3200-3650
※第31回日本プロ音楽録音賞は、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)の共通目的基金の助成を受け運営されています。

情報リンク先
日本プロ音楽録音賞
https://www.japrs.or.jp/pro_rec/
日本プロ音楽録音賞は音楽文化と産業の発展の一翼を担う録音エンジニアが制作し応募した音楽録音作品について、エンジニアが有する音楽に対する感性、技術力等を評価することにより、授賞対象優秀作品および最優秀作品並びにベストパフォーマー賞を選定し、これに携わり制作を担ったエンジニアおよびベストパフォーマーのアーティストを顕彰することでエンジニアの技術の向上と次世代エンジニアの発掘を図ることを目的とし、表彰を行うものです。
「第31回 日本プロ音楽録音賞」は、9月1日(月)から9月30日(火)まで作品の応募を行い、12月5日(金)「音の日」(※本来は12月6日ですが、土曜日につき1日前倒し)に授賞式の開催を予定しております。
一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)
https://sartras.or.jp/
ICTを活用した教育の未来と、ICTを活用した教育で用いられる著作物の著作権者、著作隣接権者を支える団体です。
記事内に掲載されている価格は 2025年9月12日 時点での価格となります。
最新記事ピックアップ